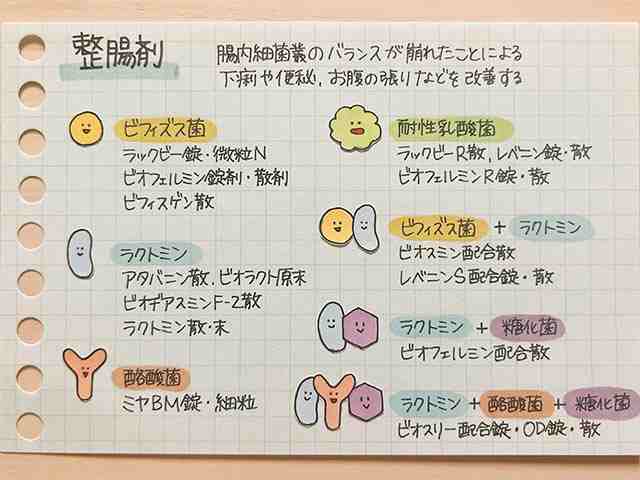【最新版】心不全治療薬を徹底解説

前回は不全の分類LVEFについて解説しました。心不全の治療薬は、LVEFに基づいて選択されることが推奨されています。心不全は、初回評価による左心室駆出率によって、LVEFの低下した心不全(HFrEF)、LVEFの保たれた心不全(HFpEF)などに分類されます。
今回は、最新のガイドラインに基づき、HFrEFやHFpEFに用いられる主な不全治療薬について解説します。
慢性心不全の治療目標
心不全患者は再入院も多く、総死亡率も高い疾患です。
入院後、1年以内の全死亡率は約20%であり、退院患者のうち1年以内の再入院率は27~29%と極めて高くなっています。また、心不全増悪による入院から4年間での生存率は49%であり、心不全で入院した患者の約半数は、4年以内に死亡します。
慢性心不全の治療目標は、生命予後の改善、再入院予防、症状・QOLの改善、突然死の予防です。特にHFrEFにおいては、生命予後や再入院抑制効果が証明された β遮断薬、ACE阻害薬/ARB、MRA、ARNI、SGLT2阻害薬 が基本治療薬として使用されます。
これらを適切に導入し、組み合わせることで、心不全の進行を抑えて、予後を改善することが重要であり、薬剤の選択と管理が治療の鍵となります。
※「2025 年改訂版 心不全診療ガイドラインP64 図24の『心不全治療のアルゴリズム』」を参照すると理解が深まります。
心不全治療薬はSGLT2阻害薬、β遮断薬、ACE阻害薬/ARB、MRA、ARNIの5つに大別される
心不全治療薬「SGLT2阻害薬」の特徴
「SGLT2阻害薬(ダパグリフロジン、エンパグリフロジン)」は、もともと糖尿病治療薬として開発されましたが、糖尿病の有無にかかわらず、従来の心不全治療(ACE阻害薬/ARB、β遮断薬、MRA)にSGLT2阻害薬を追加することで、HFrEF患者の心不全悪化や心血管死のリスクが低下することが示されています。
一方、HFpEFに対する薬物治療についてはこれまで有効な選択肢が乏しい状況でしたが、2021年以降にSGLT2阻害薬の効果が明らかとなり、最新のガイドラインでは「心不全入院または心血管死のイベント抑制を目的としたエンパグリフロジンもしくはダパグリフロジンの投与は、禁忌のないすべての症候性HFpEF患者に対して推奨される」と大きな変更がありました。
これにより、SGLT2阻害薬は、LVEFに関わらずクラスIの推奨となり、心不全治療薬としてより多くの患者さんに処方されることが予想されます。
SGLT2阻害薬の特徴は、近位尿細管でのグルコース再吸収を抑えることで、血糖を下げながら利尿作用を発揮する点です。また、心筋のエネルギー代謝改善、腎保護作用、ヘマトクリット上昇など多面的な作用が心不全改善に寄与すると考えられています。
心不全治療薬「β遮断薬」の特徴
「β遮断薬」は HFrEFの全重症度で使用され、生命予後改善が証明されています。また、心不全症状のない心筋梗塞後患者にも有効です。さらに、頻脈性心房細動合併例では心拍数コントロールにも用いられます。
β遮断薬は交感神経系の抑制など心拍数低下(陰性変時作用)や心拍出量の低下(陰性変力作用)作用を有するため、以前は収縮能が低下した心不全に対して禁忌と考えられていました。
しかし、多くの大規模臨床試験で心保護効果が証明され、現在は心不全治療の基本薬となっています。その詳細な機序は不明とされていますが、心拍数減少によるエネルギー消費抑制、拡張期特性の改善、レニン抑制による体液貯留抑制、心筋傷害抑制、抗不整脈作用などが考えられています。
心不全治療薬「ACE阻害薬/ARB」の特徴
ACE阻害薬はHFrEFの全重症度で使用され、生命予後改善が証明されています。
HFrEFの治療では第一選択薬であり、β遮断薬の有効性もACE阻害薬併用下で証明されていることは留意すべき点です。