慢性腎臓病(CKD)患者の食事療法に「ポリスチレンスルホン酸」を使う理由って?

2024年の推計では、日本の慢性腎臓病(CKD)の患者数は約2000万人(成人の5人に1人)となっています。CKDは心血管死や全死亡のリスクを増やし、生命を危険に晒します。CKDは腎臓の機能が段々と低下していく進行性の疾患で、病の進行を遅くすることが治療の中心です。CKDの進行は、生活指導・食事療法・薬物療法によって遅らせることができます。1)
CKDの進行に伴って、食事や運動についての制限が変化していきます。特に糖尿病や高血圧を合併したCKD患者の栄養指導はCKDステージによって大きく変化するため注意が必要です。本記事では、CKD療養中の生活指導・食事療法について解説します。
CKD患者への生活習慣指導
CKDの進行を抑えるために、禁煙・節酒・適度な睡眠時間・口腔ケア・ワクチン接種が推奨されています。また、肥満を伴わないCKD患者は日常的な運動を行うことも良いとされています。1)
ただし、運動量には合併症や身体機能に配慮が必要です。透析患者は水分摂取量が制限されていることが多いですが、CKD患者は、体液過剰がない限り、基本的に水分制限は行われません。1)
腎臓は脱水には比較的脆弱な臓器のため、脱水の危険がある夏場などは水分摂取をするようにすすめてください。
CKD患者への食事管理指導の基準とは?
CKDの進行は食事療法によって遅らせることができますが、CKDのステージごとに食事療法の基準が定められています(表1)。具体的な管理目標は、糖尿病や肥満、サルコペニア・フレイルなどの合併する疾患に応じて調整されます。
(表1)CKDステージによる食事療法基準1)
| ステージ (GFR) |
エネルギー (kcal/kgBW/日) |
たんぱく質 (g/kgBW/日) |
食塩 (g/日) |
K (mg/日) |
| G1 (GFR≧90) |
25~35 | 過剰な摂取をしない | <6.0 | 制限なし |
| G2 (GFR 60~89) |
過剰な摂取をしない | 制限なし | ||
| G3a (GFR 45~59) |
0.8~1.0 | 制限なし | ||
| G3b (GFR 30~44) |
0.6~0.8 | ≦2,000 | ||
| G4 (GFR 15~29) |
0.6~0.8 | ≦1,500 | ||
| G5 (GFR < 15) |
0.6~0.8 | ≦1,500 |
「CKD診療ガイド2024」を基に筆者が作成
(注:エネルギーや栄養素は合併症や性別、年齢、身体活動度に応じて適正量を個別に調整する。体重は基本的に標準体重を用いる)
表1にもあるように、CKDステージが進行すると、特にタンパク質とカリウムの制限が厳しくなっていきます。
腎機能が正常な場合、タンパク質は尿の中に漏れ出ることはほとんどありません。しかし、腎臓に過剰な負担がかかったり、腎臓の機能が一部破綻したりしていると、尿中にタンパク質が漏れ出ることがあります。
蛋白尿は末期腎不全のリスク因子のため、タンパク質の過剰な摂取が制限されています。タンパク質は肉類や卵、乳製品に多く含まれています。2)
また、腎臓は体内の過剰なカリウムを排泄するため、腎機能が低下するにつれて血清カリウム値が基準値を超えやすくなります。高度の高カリウム血症は心停止の危険があります。1)カリウムは生野菜や果物、芋類、大豆、藻類に多く含まれています。2)
CKDを進行させる高血圧と糖尿病患者の食事指導方法
高血圧と糖尿病はCKDを進行させる代表的な原因疾患です。高血圧と糖尿病の患者へは、以下のように食事指導が行われます。



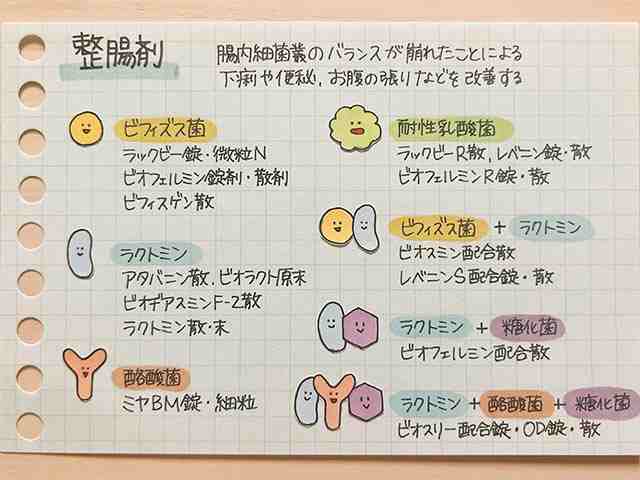



































.jpg?1743033189)