【2024年度改定版】使用薬剤料の算定要件や計算方法をわかりやすく解説

使用薬剤料は通常パソコンで自動計算されるため、ご自身で計算する機会はほとんどないでしょう。しかし、レセコンの不具合や災害時など、システムが使えなくなった場合は手動で計算する必要があります。患者から金額について質問を受けることもあるため、計算方法を知っておくことは大切です。
本記事では、使用薬剤料の算定要件や計算方法、算定の際の留意点を解説していきますので、一緒に計算練習をしてみてください。
使用薬剤料とは
使用薬剤料とは、処方・調剤された薬の価格(円)を保険請求するために点数化したもののことです。
薬価は品目ごとに厚生労働大臣により定められており、その単位は「円」です。調剤報酬は「点」で計算されるため、薬価の「円」から薬剤料の「点」に変換する必要があります。使用薬剤料は通常レセコンで自動計算されますが、手動で算出することも可能です。
使用薬剤料の算定要件
使用薬剤料の算定要件および点数は以下のとおりです。
- 使用薬剤の薬価が薬剤調整料の所定単位につき15円以下の場合:1点
- 使用薬剤の薬価が薬剤調整料の所定単位につき15円を超える場合:10円またはその端数を増すごとに1点
参照:別表第三 調剤報酬点数表 /厚生労働省
つまり、薬剤ごとに決められている薬価から所定単位ごとの金額を計算し、それに従って使用薬剤料の点数を算出する必要があります。
文章だけでは分かりにくいと思いますので、後ほど具体的な処方例を用いて計算方法やルールを確認していきます。一緒に練習をしてご自身でも計算ができるようになっていきましょう。
所定単位とは
算定要件に示されている所定単位とは、薬の種類ごとに以下のように定められています。
| 薬の種類 | 所定単位 |
| 内服薬 | 1剤1日分 |
| 内服用滴剤 | 1調剤分 |
| 頓服薬 | 1調剤分 |
| 外用薬 | 1調剤分 |
参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省
なお、所定単位の「1剤」「1調剤」については以下のように考えましょう。
内服薬の「1剤」:服用時点が同じもの
内服用滴剤の「1調剤」:服用時点と処方日数が同じもの
外用薬の「1調剤」:1薬品1調剤
「1剤」や「1調剤」の考え方については薬剤調製料の記事でも詳しく説明を行っていますので、こちらもあわせてご覧ください。
多剤投与時の減算措置について【2024年度改定】
2024年度の診療報酬改定において、特別基本料AまたはBを算定する薬局で多剤調剤を行う際は、薬剤料が減算されるという変更が加えられました。
対象となるのは内服薬のみであり、1回の処方箋受付のうち、7種類以上の内服薬の調剤を行った場合、所定点数の90%に相当する点数を算定することとされています。
「所定点数」とは、1回の処方箋受付のうち、所定単位ごとの内服薬の薬剤料(単位薬剤料に調剤数量を乗じて得た点数)のことをいいます。
参照:別表第三 調剤報酬点数表 /厚生労働省
内服薬の種類と数え方
内服薬の種類を数える際のルールは以下の通りです。
(イ) 内服薬の種類に屯服薬は含めない。
(ロ) 錠剤、カプセル剤については、1銘柄ごとに1種類と計算する。
(ハ) 散剤、顆粒剤、液剤、浸煎薬及び湯薬については、1銘柄ごとに1種類と計算する。
(ニ) (ハ)の薬剤を混合して服薬できるよう調剤を行ったものについては、1種類とする。
(ホ) 同一保険医療機関における異なる診療科の複数の保険医が発行する処方箋を同時に受け付けた場合は、それぞれの処方箋の内服薬の「種類」を合計して計算する。
参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省
使用薬剤料の計算方法
ここからは、いよいよ使用薬剤料の計算方法について詳しく確認をしていきましょう。
薬の種類ごとに異なる部分もありますが、基本的な流れは同じです。後で出てくる処方例を使用して、実際にご自身でも計算をしてみてください。
使用薬剤料の計算の流れ
① 「所定単位の薬価」を計算する。
薬ごとに厚生労働大臣が定めている薬価を使用し、以下の所定単位分の金額を計算する。
② 「円」を「点」に変換する。
「所定単位の薬価(円)」÷10をして単位を「点」にする。
この際、五捨五超入の考えに従うことがポイント。
③ 点数に投与単位をかける。
所定単位の点数が求められたら、最後に投与単位をかけて総投与量の薬剤料を求める。
なお、薬の計算に用いる所定単位と投与単位はそれぞれ以下の通りです。
| 薬の種類 | 所定単位 × 投与単位 |
| 内服薬 | 1剤1日分 × 日数 |
| 内服用滴剤 | 1調剤分 × 調剤数 |
| 頓服薬 | 1調剤分 × 調剤数 |
| 外用薬 | 1調剤分 × 調剤数 |
五捨五超入とは
手順②の「円」から「点」に変換する際に行う五捨五超入とは、薬剤料を起算した時の端数を処理する方法です。
調剤報酬の算定点数には小数点以下が存在しないため、整数にする必要があります。四捨五入のような考え方ですが、五捨五超入では「5」以下である場合は切り捨て、「5」を超えた場合は切り上げます。
五捨五超入の考え方
| 薬価 | 10で割った値 | 薬剤料 |
| 204.9円 | 20.49 | 20点 |
| 205円 | 20.5 | 20点 |
| 205.1円 | 20.51 | 21点 |
それでは、ここからは実際の処方例を見ながら計算練習をしてみましょう。
薬の種類ごとに所定単位や投与単位が変わりますが、基本的な計算方法の考え方については共通であり、先ほどの①〜③の手順に従ってそれぞれ使用薬剤料を計算します。
内服薬の計算例
内服薬に関しては2つの例を見ていきましょう。
処方例1
A錠 2錠 (6.5円/錠)
B錠 2錠 (15.1円/錠)
1日2回 朝・夕食後 7日分
① 「所定単位の薬価(1剤1日分)」を計算する。
(6.5円×2錠)+(15.1円×2錠)=43.2円
② 「円」を「点」に変換する。
43.2円÷10=4.32点→4点(小数点以下が5以下のため切り捨て)
③ 点数に投与単位(日数)をかける。
4点×7日分=28点
よって上記処方の使用薬剤料は28点です。
処方例2
A錠 3錠 (13.3円/錠)
Bカプセル 3Cp (28.5円/Cp)
1日3回 毎食後 5日分
C散 2g (8.6円/g)
1日2回 朝・夕食後 5日分
2剤以上ある時はそれぞれ使用薬剤料を計算し、最後に合算します。
① 「所定単位の薬価(1剤1日分)」を計算する。
(13.3円×3錠)+(28.5円×3Cp)=125.4円
(8.6円×2g)=17.2円
② 「円」を「点」に変換する。
125.4円÷10=12.54点→13点(小数点以下が5を超えるため切り上げ)
17.2円÷10=1.72点→2点(小数点以下が5を超えるため切り上げ)
③ 点数に投与単位(日数)をかける。
13点×5日分=65点
2点×5日分=10点
処方全体の使用薬剤料は65点+10点=75点です。
内服用滴剤の計算例
処方例
A剤 2本(10mL/本) (7.5円/mL)
就寝前 1回15滴
① 「所定単位の薬価(1調剤分)」を計算する。
7.5円×10mL×2本=150円
② 「円」を「点」に変換する。
150円÷10=15点
③ 点数に投与単位(調剤数)をかける。
15点×1=15点
よって、上記の内服用液剤の処方は15点です。
頓服薬の計算例
【処方例】
A錠 1回1錠 5回分 (13.5円/錠)
頭痛時
① 「所定単位の薬価(1調剤分)」を計算する。
13.5円×5錠=67.5円
② 「円」を「点」に変換する。
67.5円÷10=6.75点→7点(小数点以下が5を超えるため切り上げ)
③ 点数に投与単位(調剤数)をかける。
7点×1=7点
よって、上記の頓服薬の使用薬剤料は7点です。
外用薬の計算例
処方例
A軟膏 10g (15.5円/g)
Bクリーム 15g (40.3円/g)
上記混合 1日1回 腰に塗布
① 「所定単位の薬価(1調剤分)」を計算する。
(15.5円×10g)+(40.3円×15g)=759.5円
② 「円」を「点」に変換する。
759.5円÷10=75.95点→76点(小数点以下が5を超えるため切り上げ)
③ 点数に投与単位(調剤数)をかける。
76点×1=76点
よって、上記の処方の使用薬剤料は76点です。
使用薬剤料を算定する際の留意点5つ
薬自体にかかる使用薬剤料の算定方法だけではなく、その他発生する費用の患者する徴収の可否についても知っておきましょう。
1.薬剤の容器代の徴収【2024年度改定】
2024年度の診療報酬改定で、薬剤交付時の容器代の徴収について変更が加えられました。
以前は、薬剤交付の際に容器を使用し、その後患者から再利用可能なものを返還された場合には徴収した実費を返還することとされていました。
しかし、衛生上の理由から一度他の患者に使用した容器を別の患者に改めて使用することは行われていないのが現状でした。
そこで2024年度の診療報酬改定では、当該実費返還に関する文言は削除され、「投薬時において薬剤の容器を交付する場合は、その実費を徴収できる」と改められています。
もともと薬が入っているチューブや使い捨てのタイプの容器に関しては、そのまま投薬するため容器代を徴収することはできません。
参照:令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】 /厚生労働省
2.吸入治療に使用する器具代の徴収
喘息治療剤のための小型吸入器や噴霧器などを交付した場合は、機器の実費を徴収することができますが、返還された場合は実費も返還しなければなりません。



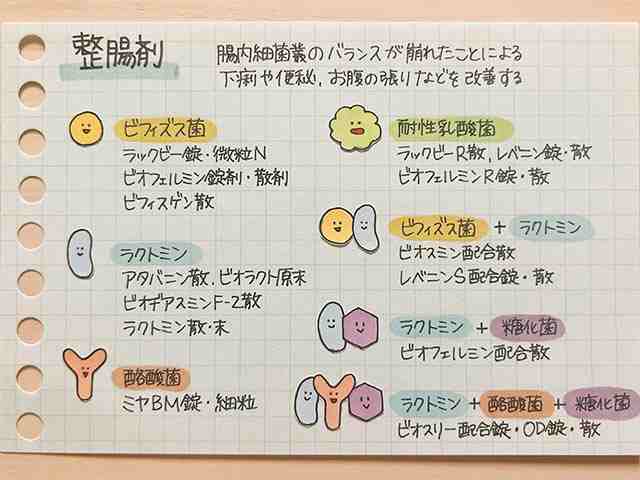
















.png?1764143611)




















.jpg?1743033189)