電子カルテ情報共有サービスとは? 医療DX加算算定の新要件を解説

「薬局のアンテナ」のてっちゃんです!
今回は医療DX推進体制整備加算(以下、医療DX加算)において、令和7年10月より導入が必須となる「電子カルテ情報共有サービス」を取り上げます。
医療DX加算の施設基準では以下の様に定められています。
施設基準(6)
国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。(令和7年9月30日までは経過措置)
つまり、医療DX推進体制整備加算を令和7年10月以降に算定する場合は、「電子カルテ情報共有サービス」の導入が必要ということです。
そこで今回は、電子カルテ情報共有サービスについて多く寄せられるご質問にQ&A方式でお答えしていきます。
Q1.そもそも電子カルテ情報共有サービスって何?
電子カルテ情報共有サービスとは、「医療機関で記録された電子カルテ情報の一部を、マイナ保険証を利用することで、全国の他の医療機関等(薬局を含む)が閲覧できる仕組み」です。
現在、オンライン資格確認等システムが稼働していますが、そのおかげで薬剤情報や特定健診の情報、処方情報などの患者情報を薬局で閲覧出来るようになっています。
今後、電子カルテ情報共有サービスが稼働すると、これらに加えてさらに、健康診断結果報告書や臨床情報(傷病名・検査・感染症・アレルギー等・処方)が閲覧可能となります。
電子カルテ情報共有サービスのイメージを以下に示します。

引用元:電子カルテ情報共有サービス 概要案内 /厚生労働省
Q2.薬局にどんなメリットがあるの?
薬局が電子カルテ情報共有サービスを導入することで、これまで閲覧出来ていた薬剤情報や特定健診情報、処方(調剤)情報に加えて、「健診結果報告書」「臨床情報」も閲覧できるようになります。
健診結果報告書の閲覧方法
現在、オンライン資格確認等システムを導入している場合、薬局で特定健診の情報を閲覧する事が出来ます。(マイナ保険証による同意が必要)
一方で、オンライン資格確認等システムで閲覧出来る特定健診情報には以下の課題があります。
➀半年~1年前の情報であることも多く、情報が古い
➁特定健診以外の健診(企業健診や人間ドックなど)に対応しきれていない
電子カルテ情報共有サービスでは、これらの課題を解決する事が期待されています。
電子カルテ情報共有サービスで「健診結果報告書」を閲覧する仕組みは、以下の通りです。

引用元:第22回 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ 2024(令和6)年6月10日 /厚生労働省
医療機関から直接電子カルテ情報共有サービスに健康診断の情報を入れることで、様々な健康診断の情報をタイムリーに共有することが出来ます。
なお、健康診断の項目自体は特定健診の項目とさほど変わりません。

引用元:電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書 /厚生労働省
臨床情報とはどのような情報か?
電子カルテ情報共有サービスを導入することで、健診結果報告書だけでなく「臨床情報」も閲覧可能となります。
「臨床情報」とは➀傷病名、➁薬剤アレルギー等、③その他アレルギー等、④感染症、⑤検査(救急・生活習慣病)、⑥処方の6つの情報の総称です。
電子カルテ情報共有サービスで「臨床情報」を閲覧する仕組みは以下の通りです。

引用元:第22回 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ 2024(令和6)年6月10日 /厚生労働省
それぞれの情報の詳細はここでは割愛しますが、これまで以上に多くの情報が閲覧可能になることはご理解頂けるかと思います。
例えば傷病名など、患者へ告知していないケースや他の医療機関へ共有することが望ましくないケースもありますので、臨床情報の閲覧に一定の制限をかけることもできるようになっています。
健診結果報告書と臨床情報を閲覧するには
健診結果報告書と臨床情報は、医療機関の電子カルテの情報です。
その情報を閲覧するには、情報提供側である医療機関が、電子カルテ情報共有サービスを導入している必要があります。



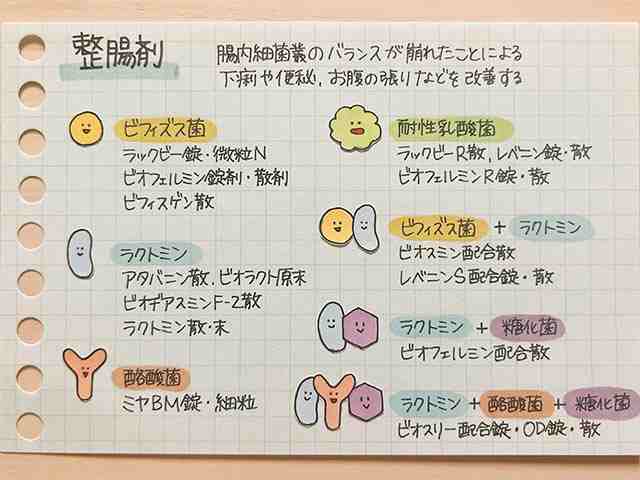
.jpg?1710295025)







































.jpg?1743033189)