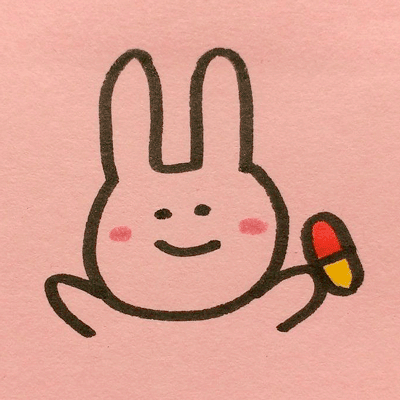SDA・DSAを徹底解説!非定型抗精神病薬ってどんな薬?


精神科領域でよく処方される「抗精神病薬」。とくに最近使われることが多いのが、「第二世代抗精神病薬(非定型)」と呼ばれる薬剤です。私を含め、この分野に苦手意識のある方は多いのではないでしょうか。今回は基本からまとめました。
非定型抗精神病薬(第二世代抗精神病薬)とは?
第二世代抗精神病薬、いわゆる非定型抗精神病薬は、統合失調症の第一選択薬として使用される薬剤です。
多くの第二世代薬は、ドパミンD₂受容体遮断に加え、セロトニン5-HT₂A受容体拮抗作用を併せ持っており、この作用のバランスによって副作用を抑えながら治療効果を得られると考えられています。
また、薬剤によっては統合失調症の他に、うつ病や双極性障害などへの適応があるものもあります。
【統合失調症とは?】
統合失調症は、幻覚・妄想といった「陽性症状」、意欲の低下・感情の平坦化といった「陰性症状」がみられる精神疾患です。これらの症状にはドパミンとセロトニンが関与していると考えられています。
中脳辺縁系でドパミンの作用が過剰になると陽性症状を起こし、中脳皮質系でセロトニンが作用してドパミンの放出が抑制されると陰性症状を示します。思春期〜青年期に発症することが多く、慢性化しやすいため、長期的な薬物治療と支援が必要です。
第一世代抗精神病薬との違い
第一世代抗精神病薬と第二世代では下記のような違いがあります。
抗精神病薬 第一世代と第二世代の比較表
| 比較項目 | 第一世代(定型) | 第二世代(非定型) |
| 作用機序 | D₂受容体を強力に拮抗 | D2拮抗+ 5-HT2A拮抗 |
| 陽性症状への効果 | 強い | 強い |
| 陰性・認知症状への効果 | 限定的 | 改善効果を期待できる |
| 錐体外路症状(EPS) | 高頻度 | 比較的少ない |
| 高プロラクチン血症 | 起こりやすい | 一部薬剤で起こる |
錐体外路症状(EPS)とはD₂受容体を強く遮断することによって起こるものです。
動作が遅くなったり手足が小刻みに震えたりするパーキンソニズム、手足がムズムズするアカシジア、口がモグモグするなどのジスキネジア、勝手に筋収縮が起こるジストニアといった症状が見られます。
5-HT2Aを遮断することでドパミンの過剰な抑制が軽減されるためEPSの頻度が減少します。
SDA(セロトニン・ドパミン拮抗薬)とは?

SDAは、5-HT₂A拮抗とD₂拮抗を主要な作用機序とするグループで、第二世代抗精神病薬の中でも初期に登場した薬剤群です。陽性症状にしっかり効きつつ、EPSを抑えられるよう工夫されています。