MARTA・DSS・SDAMの特徴は?第二世代抗精神病薬の使い分け


前回は第一世代との違いや「SDA」、「DSA」についてまとめましたが、今回はその他の第二世代抗精神病薬である「MARTA(多元受容体標的化抗精神病薬)」、「DSS(ドパミンシステムスタビライザー)」、「SDAM(セロトニン・ドパミンアクティビティモジュレーター)」の薬剤についてまとめました。特徴を確認しましょう。
第二世代抗精神病薬「MARTA(多元受容体標的化抗精神病薬)」とは?4剤の一覧表でおさらい

「MARTA(多元受容体標的化抗精神病薬)」は、ドパミン(ドーパミンD2)D2・セロトニン5-HT2A受容体だけでなく、アドレナリンα・ムスカリンM・ヒスタミンH1受容体にも作用するという特徴があります。
複数の受容体に作用することで、陰性症状や不安などの症状にも効果を示します。
錐体外路症状は少ないものの、体重増加や代謝障害といった副作用が出やすいです。4つの薬剤の特徴を押さえておきましょう。
オランザピン(ジプレキサ)
統合失調症の他に、双極性障害における躁症状及びうつ症状、抗悪性腫瘍剤投与に伴う消化器症状にも適応があります。食事の影響はなく、1日1回の服用で効果が持続します。
注意点としては、体重増加と代謝障害(糖尿病や脂質異常症)のリスクが高いことが挙げられます。そのため、糖尿病や糖尿病の既往のある患者には禁忌です。
併用薬のチェックや患者への聞き取りを忘れずに行いましょう。また、特に若い患者さんでは体重増加による服薬中断が多いため、食事や運動についても積極的にアドバイスしたいところです。
クエチアピン(セロクエル、ビプレッソ)
「クエチアピン製剤」には、1日2~3回服用する「セロクエル」と、徐放性製剤で1日1回就寝前に服用する「ビプレッソ」があります。
この2つは適応も異なり、セロクエルは統合失調症に、ビプレッソは双極性障害におけるうつ症状に適応があります。
頻度の高い副作用としては、起立性低血圧と傾眠、不眠があります。また、オランザピン同様に著しい血糖値上昇のリスクがあるため、糖尿病や糖尿病の既往のある患者には禁忌です。
クロザピン(クロザリル)
適応が「治療抵抗性統合失調症」であり、他の抗精神病薬治療に抵抗を示す場合のみ使用できます。陽性症状だけでなく、陰性症状や抑うつ症状にも効果を示します。
優れた効果の一方で、無顆粒球症や心筋炎、代謝障害などのリスクがあります。そのため、「CPMS(クロザリル患者モニタリングサービス)」による厳格な管理下でのみ使用されます。
服薬指導の際は、突然の高熱、喉の痛み、だるさなどの症状が現れたらすぐに医師に連絡するよう指導しましょう。
また、「持効性抗精神病薬(リスペリドン持効性懸濁注射液やアリピプラゾール水和物持続性注射剤など)」とは併用禁忌です。なぜなら、副作用が発現したときに血中から薬剤が失するまでに時間がかかってしまうためです。




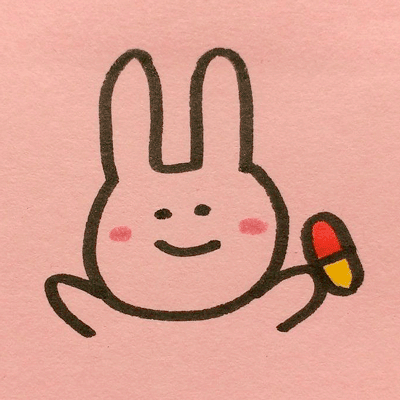


































.jpg?1743033189)


