いまさら聞けない「薬」のキホン12:遮光による保管が必要な薬剤
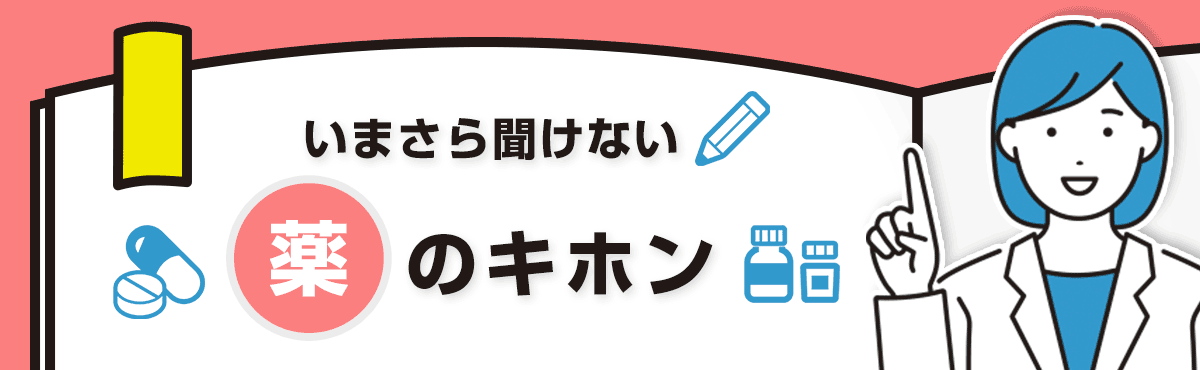
記録的猛暑に見舞われた日々が多くありましたが、医薬品においては夏だけではなく1年中『光』の影響に注意しなければならない薬があります。化学構造が複雑になる医薬品が多く発売されていることに伴い、光に不安定な医薬品が増加していますが、どのような注意が必要でしょうか。今回はそんな「遮光による保管が必要な医薬品」について見ていきましょう。
★遮光による保管が必要な薬剤One Point
そもそも「遮光」とは、内容医薬品に規定された性質及び品質に対して影響を与える光の透過性を防ぎ、内容医薬品を光の影響から保護することと定義されています1)。また、光安定性試験ガイドラインの安定性評価では120万lux・hrと定められていますが、その中でも日本で医薬品は室内光に曝されるとの考えから、白色蛍光ランプで1,000lxで約50日の照射度がオプション2として設定されています2)。
しかし、実際にはその状況下で医薬品が保管されることは多くありません。イメージとして、1,000lxは蛍光灯照明の事務所や百貨店売り場の明るさで、書類作成や診療など細かい作業ができる明るさです。患者さんの自宅の部屋の明るさとしては、リビングが200~300lx程度3)。学校薬剤師の照度環境衛生試験では、教室及び黒板の照度は500lx以上が望ましいとされています。
例えば、遮光が必要な医薬品としてセパミット-R細粒2%があります。セパミット-R細粒2%は、蛍光灯照射下(1,000lx)で72時間後には90%が分解されてしまいます4)。ちなみに急速に普及しているLED照明でも、蛍光灯ほどではないですが、遮光が必要な医薬品の色調変化が認められています5)。
そのような光源下でも対応できるよう、遮光が必要な医薬品には製造過程・調剤時・投薬後の保管時など様々な対策がありますが、このコラムでは製造過程にフォーカスを当てて違いを見ていきます。
































.png?1765758785)
.png?1765760030)
.png?1765760115)






.jpg?1743033189)