風邪薬に配合されている抗ヒスタミン薬、なぜ古い「鎮静性」のものばかり?
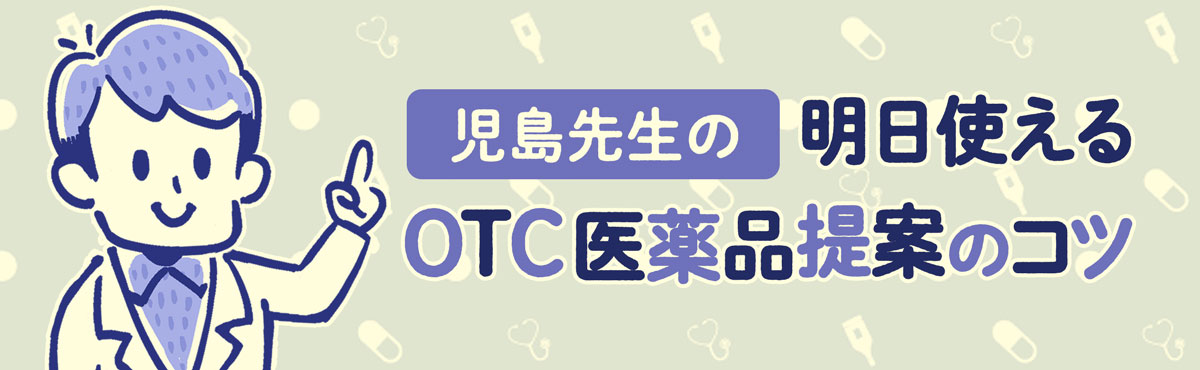
ほとんどの風邪薬(総合感冒薬)にはくしゃみ・鼻水の症状緩和を目的として抗ヒスタミン薬が配合されていますが、その抗ヒスタミン薬は全て古いタイプの「鎮静性」の薬です。そのため、眠気や抗コリン作用による緑内障や前立腺肥大への悪影響といったデメリットを避けることができません。
ではなぜ副作用の少ない、新しい「非鎮静性」の薬が使われていないのでしょうか。
今回は、そんな風邪薬にまつわる疑問について解説します。
- 風邪薬に配合されている抗ヒスタミン薬が、全て古いタイプの「鎮静性」のものである理由
- 風邪の鼻症状に対し、眠くならない対処法はどんなものがあるか
風邪薬に配合されている抗ヒスタミン薬が、古いタイプの「鎮静性」である理由
OTC医薬品として販売されている風邪薬の多くには、くしゃみ・鼻水といった鼻症状の緩和を目的とした「抗ヒスタミン薬」が配合されています。なぜなら風邪をひいたときは、ほとんどの場合で鼻症状を伴う1)からです。
この「抗ヒスタミン薬」には、古いタイプで眠くなりやすい「鎮静性」のものと、新しいタイプで眠くなりにくい「非鎮静性」のものがあります(※その中間に「軽度鎮静性」が分類されることもあります)。
OTC医薬品として用いられている抗ヒスタミン薬の分類
| 分類 | 主な薬剤 |
| 鎮静性 | クロルフェニラミン、ジフェンヒドラミン、クレマスチン、プロメタジン、ケトチフェン |
| 軽度鎮静性 | メキタジン、アゼラスチン |
| 非鎮静性 | ロラタジン、フェキソフェナジン、エバスチン、エピナスチン、セチリジン、ベポタスチン |
花粉症などのアレルギー性鼻炎の治療では、基本的に眠くなりにくい「非鎮静性」の薬を使うのがセオリーとされ2)、「鎮静性」の薬を使うことは稀です。ところが、風邪薬に配合されている抗ヒスタミン薬は、すべて「鎮静性」のものになっています。
これは、「風邪薬が新しい薬にアップデートされていないだけ」なのではなく、眠くなりやすい「鎮静性」の薬でなければならない理由があるからです。それは、風邪に伴う鼻症状の緩和には、抗ヒスタミン作用よりも抗コリン作用が大きく関わっている、という点です3)。
抗コリン作用も持ち合わせた抗ヒスタミン薬を選ぶと、どうしても古いタイプの「鎮静性」の薬になってしまいます。これが、風邪薬に配合されている抗ヒスタミン薬が、すべて「鎮静性」のものになっている主な理由です。


























.png?1764143611)















.jpg?1743033189)



