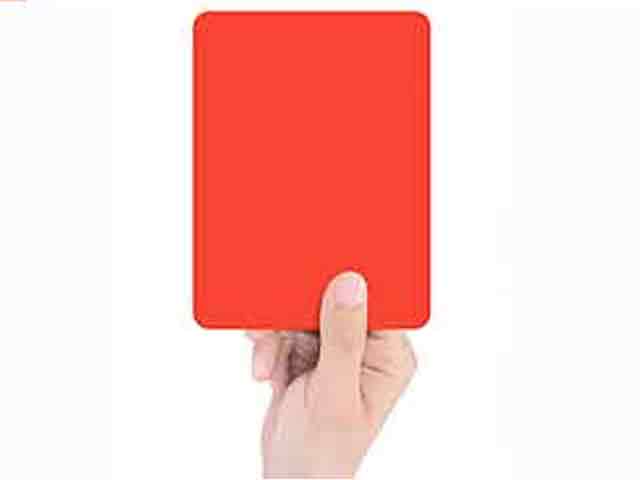専門家5人に聞く、リフィル処方箋導入の是非

海外では一般的なリフィル処方箋。日本でも導入の是非が問われていますが「薬キャリPlus+」で執筆いただいている専門家の方々はどのように考えているのでしょうか。そこで、日本の社会保障制度や医療業界の体制などを踏まえ、5人の専門家に現時点でのそれぞれの意見をうかがいました。
■専門家
藤田道男氏(医薬ジャーナリスト)/狭間研至氏(ファルメディコ株式会社代表取締役社長)/漆畑稔氏(日本ジェネリック医薬品学会理事)/髙村徳人氏(薬学博士)/藤澤節子(薬局ルンルンファーマシー代表取締役)
リフィル処方箋とは

リフィル処方箋は、一つの処方箋で複数回に渡り薬を受け取れる制度。先進国では導入している国も多い(右図)。特に、アメリカは他国よりもいち早い1951年に導入しており、現在、リフィル処方箋と新規処方箋はほぼ同じ割合で発行されている。
なお、すでに日本で導入済みの「分割調剤」との違いは、あらかじめ医師が指定した日数、量の範囲内で分割して患者に渡す、という点である。
2016年度診療報酬改定の議論では長期投薬における「分割調剤」や、「リフィル処方箋」に関する議論が行なわれる見込みだ。この2点に注目が集まったのには「残薬」の問題が背景にある。厚労省の発表によると、患者の50%以上が「薬が余った経験がある」と回答しており、さらに残薬経験者の63%が「負担額が減るなら薬の交付量を減らしてほしい」と考えているそうだ。
450億円ともいわれる日本の残薬を削減するためにもリフィル制度を導入すべきという意見がある一方、患者が医師の診察を受けないまま薬を受けることに対して安全の担保や責任の所在に対して疑問の声も多く、白熱した議論が展開しそうだ。
ここで、専門家5人の意見を見てみよう。
専門家5人に聞く、リフィル処方箋導入の是非
【質問項目】
①リフィル処方箋の導入は賛成?反対?
②その理由は?
③導入する場合、解決すべき課題は?

①賛成
②慢性疾患など長期間の服用が必要な患者に対しては、リフィル処方箋は再診の手間が省け、医療費軽減や医師の業務軽減といった効果がある。また、患者は服薬期間中の服薬ケアを任せる薬局を吟味するだろうから「かかりつけ薬局」化にもつながるだろう。そうすれば薬局間の質的競争が期待できる。
③リフィル処方箋制度では、処方薬交付時だけでなく、服薬期間中の患者ケアは薬剤師が責任を負うことになる。服薬状況、症状の変化、副作用発現の兆しなどをフォローし、必要に応じて医師への受診を勧奨することになるため、薬剤師によるバイタルチェックに代表される薬学的判断能力が問われる。同時に患者や家族、処方医に信頼される存在になれるかどうかも重要だ。

①賛成
②現在いる医師のみで、超高齢社会において急増する医療ニーズに応えることはきわめて困難。医師と薬剤師が連携して薬物治療を支えるためには、リフィル処方箋の導入は必要だと思う。医師は診断と治療方針決定を、薬剤師は正確な調剤とその後の経過観察を踏まえた前回処方の妥当性評価を行うことで、より質の高い薬物治療が可能になるだろう。
③単に「1回の処方箋を繰り返し使える」という制度では、副作用や過剰な作用を引き起こしている患者に、漫然と投薬が行われることになり、患者の安全性は担保できない。薬剤師が薬学的専門性に基づいて、血液検査データやバイタルサインを踏まえ、次回も同様の薬剤で可能か、変更が必要かを判断する能力や責任感を持つことが必要だと考えている。

①賛成
②高齢者や要介護者をはじめ、雪国や過疎地など医療機関から遠隔地に住む患者などは、通院が困難なために、医療機関を受診することなく投薬を受けている「お薬だけ」の患者が多い。医師の判断の元、一定期間「有効」な処方箋を認め、疾病や療養環境や療養内容に応じて有効期間内の再調剤を認めることで、患者負担を軽減できる。
③一つ目は「リフィル処方箋」の定義が必要。現状はいわば各自が各自の定義で「リフィル処方箋」をイメージしており、それを統一する必要がある。
二つ目は、付随するサービスの検討。リフィル処方箋によって医療機関に行く負担を軽減できても、薬局に行く手間が軽減できなければ「効果(患者の負担軽減)」は半減する。例えば郵送や宅配などのサービスを同時に導入する必要がある。
三つ目は、医療機関のフォロー体制。再診の必要が発生した際の「速やかな受診」や「服薬状況の把握」に関する工夫が不可欠だろう。

①賛成
②薬剤師による医療費削減という国策にも合致するうえ、薬剤師を薬の専門家から責任者に押し上げることができる。つまり、薬物治療効果および副作用防止に責任を持たせることになるので、薬剤師の地位向上のためにもリフィル処方箋の導入には賛成だ。
③薬剤師のフィジカルアセスメント能力が高くないとリフィル処方箋は導入しにくい。その能力を高めるには、二つの方法が考えられる。一つは、薬学部の教育課程でフィジカルアセスメントの講義と実習を増やすこと。その際にシミュレータによる病態変化を見極める実習が必須である。もう一つはフィジカルアセスメントの講習会への参加と、店舗において臨床現場即時検査(POCT)や血圧・脈拍測定などから患者の病態を評価する臨床実践を積むことだ。
また私が今主張している、患者のADMEを非侵襲的に把握して薬物治療にあたる「ADME患者アセスメント」の研究と創出に努め、薬剤師の新たな技術として導入したい。

①条件付きで賛成
②症状の変わらない慢性疾患の患者さまにとっては、薬剤師のモニタリングによるリフィル処方箋は、通院の必要もなく患者さまの利便性は高いと思う。結果として、ますます副作用情報、服薬状況などアドヒアランス、セルフディケーションの指導、フィジカルアセスメントといった、薬剤師としての資質・専門性が問われるはずだ。
一方、在宅医療を受ける患者さまの病状は日々変化している。在宅患者は、重症度の高い場合が多く、リフィル処方箋の使用は難しいように思う。
③長年在宅に関わっている薬剤師として、リフィル処方箋の使用は、症状が安定している外来患者のみの使用ならば可能だと思う。しかしそれ以前に、薬剤師の在宅への参入、質の向上といった問題の解決が先だろう。
リフィル導入の可否は薬剤師の活躍如何にかかっている
専門家5人全員が導入に対しては必要性を認めているが、制度導入にはバイタルチェックや薬学的な判断能力、患者との信頼関係構築など、薬剤師の活躍が不可欠というのが共通認識。患者にとっての利便性が高いぶん、「本当に正しい薬物治療を提供できるか」という点でリスクが伴うリフィル制度では、患者の安全は薬剤師の手に委ねられているからだ。
リフィル処方箋導入に関する議論は、薬剤師の役割について考える場といっても過言ではない。「医療費削減」のための「地域包括ケアシステム」「かかりつけ薬局」推進という大きな動きの中で、薬剤師業界がその専門性を発揮していかに貢献するか、その一挙一動に注目が集まっている。
掲載内容は、記事公開時のものであり、現時点における最新情報ではない可能性があります。