疑義解釈で在宅におけるマイナ保険証利用率の考え方が明らかに

参考記事:疑義解釈資料の送付について(その24) 令和7年4月25日 事務連絡
診療報酬の算定方法の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第 57 号)等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保医発 0305 第4号)等により、令和6年6月1日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに係る疑義解釈資料を別添1から別添3までのとおり取りまとめたので、本事務連絡を確認の上、適切に運用いただくようお願いします。
2025年4月25日付で令和6年度診療報酬改定に関する疑義解釈が公開されています。今回は医療DX推進体制整備加算に関する内容になっています。
疑義解釈資料の内容
まずは簡単に今回の疑義解釈資料の内容について紹介したいと思います。資料には別添1〜3が記載されていますが、調剤報酬に関連するのは別添3(調剤報酬点数表関係)になります。そのまま掲載すると長くなるので一部省略して簡単にまとめてみたいと思います(原文は資料 をご確認ください)。
問1 医療DX推進体制整備加算の施設基準の1つであるマイナ保険証利用率は、原則3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率(社会保険診療報酬支払基金から報告されるもので外来患者がマイナ保険証を利用した場合のみが反映)」を使用することとされている。当該利用率には通常の外来患者がマイナ保険証を利用した場合のみが反映されているが、在宅患者がマイナ保険証を利用した場合はどのように対応すべきか。
(答)令和7年4月から同年9月の間の加算区分の判定(令和7年4月までの実績に限り)には、レセプト件数ベースマイナ保険証利用率の分母(社会保険診療報酬支払基金が通知する「外来レセプト件数」)から、当該月において一度でも在宅に関する管理料※を算定したレセプト件数を引いた数(在宅患者訪問薬剤管理指導料等を除くレセプト件数)を分母として算出した値を、レセプト件数ベースマイナ保険証利用率として使用してもよい。
なお、令和7年5月以降の実績については、居宅同意取得型のオンライン資格確認によるマイナ保険証利用件数が社会保険診療報酬支払基金から通知するマイナ保険証利用率集計に含まれるよう対応予定であるため、このような補正は不要となる。
※在宅に関する管理料:在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費
<計算方法>
〇 例えば、令和7年4月適用分については、令和6年11月から令和7年1月までのマイナ保険証利用率(令和7年3月に社会保険診療報酬支払基金から通知)について、以下の計算式により計算可能。

だいぶ簡素化してまとめましたが、それでもまだわかりにくいですよね。そこで背景も含めて少し詳しく説明したいと思います。
医療DX推進体制整備加算とは?
まずは医療DX推進体制整備加算についての復習です。詳しく知りたい方はこちらの記事(令和7年4月からの医療DX推進体制整備加算 - ぺんぎん薬剤師とはじめる!薬剤師のための中医協講座)を参照してください。
医療DX推進体制整備加算は令和6年度診療報酬改定で新設された「医療DXの推進に取り組む薬局を評価する点数」で施設基準を満たす薬局が届け出ることで算定可能な調剤基本料の加算(月1回のみ)です。令和6年10月1日からはマイナ保険証利用率の実績が施設基準に加わり、その実績に応じて評価が3段階に分けられています。マイナ保険証利用率の実績は医療DX推進体制整備加算を算定する月の3月前のものが用いられますが、その前月(4月前)もしくは前々月(4月前)の実績を用いることも可能です。令和7年4月からはマイナ保険証利用率の実績について見直しが行われ、それに伴い、点数も改められています。
令和7年4月〜9月 医療DX推進体制整備加算の点数とマイナ保険証利用率の実績
| 医療DX推進体制整備加算 | 点数 | マイナ保険証利用率 |
| 「1」 | 10点 | 45%以上 |
| 「2」 | 8点 | 30%以上 |
| 「3」 | 6点 | 15%以上 |
在宅におけるマイナ受付=居宅同意取得型のオンライン資格確認とは?
薬局に来局された場合とは異なり、在宅においては顔認証付きカードリーダーによる本人確認(ならびに資格確認)を行うことが難しいため、マイナ在宅webやマイナ資格確認アプリを用いた本人確認を行います(マイナ在宅webは暗証番号が必須ですがマイナ資格確認アプリでは暗証番号に加えて目視確認による認証可能です)。在宅にNFC(Near Field Communication )機能が搭載されたノートPCやスマートフォン、タブレット端末を持って行くことで、訪問先で資格確認を行うことが可能です。オンライン資格確認を導入していれば在宅での資格確認自体は行うことが可能ですが、レセプトコンピュータと連携させるにはシステム改修が必要です。
居宅同意取得型のオンライン資格確認の場合、2回目からは再照会機能を利用することが可能です。継続的に患者の居宅を訪問して医療の提供を行う在宅医療においては、なりすましが発生するリスクが極めて低く、加えてお互いの信頼関係が構築されているという前提のもと、1度居宅同意取得型のオンライン資格確認を行えば、2回目以降は本人確認なしに資格情報等を確認(再照会)することが可能となります。これにより、患者の居宅を訪問する前に資格確認を実施、資格情報を確認した上で在宅での調剤を行うことができます。
マイナ保険証利用率と居宅同意取得型のオンライン資格確認
ただ、ここで問題となるのが、疑義解釈の「問」にも書いてある(当該利用率には通常の外来患者がマイナ保険証を利用した場合のみが反映されている)ように、現状では居宅同意取得型のオンライン資格確認はマイナ保険証利用率の分子に含まれなくなっています。これにより、在宅を中心に調剤業務を行っている薬局においては資格確認を行っていてもマイナ保険証利用率を上げることができず、医療DX推進体制整備加算の施設基準を満たすことができない、仮に満たしていてもより高い点数の要件を満たすことができない状況にありました。











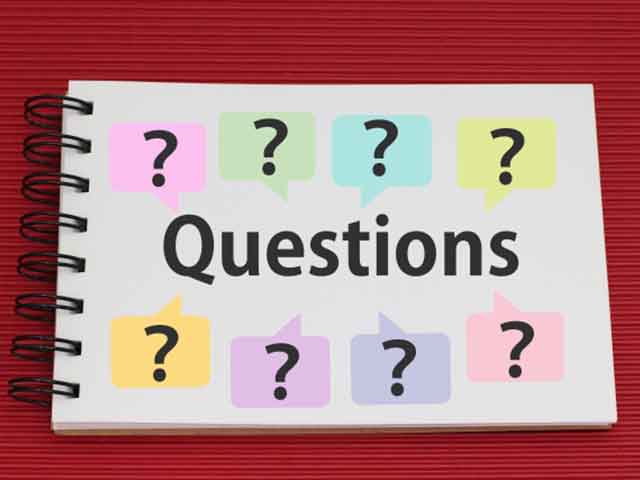


.jpg?1744676804)



















.jpg?1743033189)

