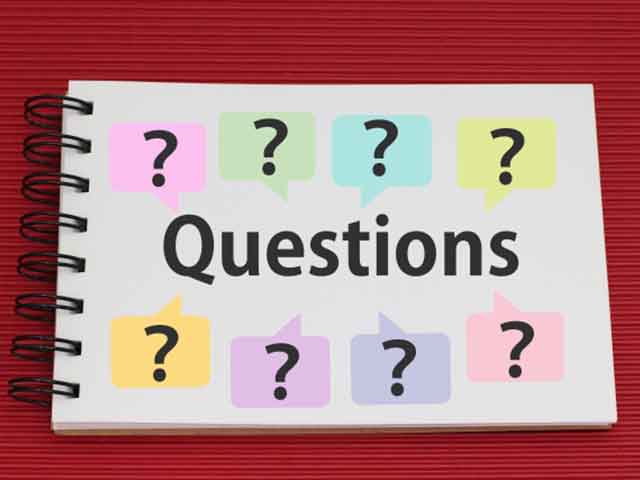報酬改定により変わる薬剤師と患者の関係

少子高齢化が進む日本の医療の基盤再編のため、地域包括ケアシステムを根底に厚生労働省が掲げた「患者のための薬局ビジョン」。この方針にのっとって、2年に一度の診療報酬改定が行われています。薬剤師業務の見直し、評価制度の検討、薬局経営の変化など、日々改定に関するニュースを気にしている薬剤師も多いと思います。今後、薬局や薬剤師のあり方はどう変わっていくのか。今年の報酬改定の最新動向についてまとめました。
厚生労働省の資料によると、薬局ビジョンの概要は以下のように記されています。
薬局の薬剤師が専門性を発揮して、ICTも活用し、患者の服薬情報の一元的・継続的な把握と薬学的管理・指導を実施する。これにより、多剤・重複投薬の防止や残薬解消なども可能となり、患者の薬物療法の安全性・有効性が向上するほか、医療費の適正化につながる。
要するに(おおまかに言うと)、現状、多くの患者が門前薬局で薬を受け取っていますが、これからは患者はどの医療機関を受診しても身近にある「かかりつけ薬局」に行き、薬の管理や服薬指導を薬剤師が行うというものです。
薬剤師は、このように「かかりつけ」になることによって在宅でのサポートをしつつ、その患者が重複している薬のチェックや飲み忘れなどがないように、しっかり服薬状況を把握していくことになります。
それに伴い、患者は処方に関して次の5つのサポートを受けられるようになります。
- 複数診療科を受診した場合でも、多剤・重複投薬等や相互作用が防止される
- 薬の副作用や期待される効果の継続的な確認を受けられる
- 在宅で療養する患者も、行き届いた薬学的管理が受けられる
- 過去の服薬情報等が分かる薬剤師が相談に乗ってくれる。また、薬について不安なことが出てきた場合には、いつでも電話等で相談できる
- かかりつけ薬剤師からの丁寧な説明により、薬への理解が深まり、飲み忘れ、飲み残しが防止される
患者は包括的かつ継続的なサポートが受けられるようになるため、これまでよりも薬剤師が身近な存在となるのではないでしょうか。
以上が、薬局ビジョンの方針に掲げられている「患者本位」という言葉の中身です。地域での在宅医療がさらに普及していくと、薬剤師としての「やりがい」も目の前の患者を通して変わっていくかもしれません。
「患者のための薬局ビジョン概要」より一部引用
詳細は、リンクより本記事をお読みください。
【福島】「在宅は患者と医療職への貢献だけでなく、薬剤師のやりがいも創出」‐藤田元・福島県薬剤師会常務理事に聞く◆Vol.2
2019年12月16日 (月)配信m3.com地域版












.png?1765760115)