「コロナ禍で加速、薬剤師の真価とは」

「患者のための薬局ビジョン」を実現するための好機といえるわけですね。
そうです。私は薬局にもようやくマーケティング的要素が出てきたと考えています。いまの「薬局2.0」にはマーケティングが必要ありません。医療機関の門前で患者さんを待っていればいいのです。集患のマーケティングは医療機関がやってくれます。しかし実は、昔の「薬局1.0」は100%マーケティングだったのです。私の親が経営していた時代の薬局は、近所のなじみのお客さんに来てもらうために、新春セールなどいろいろなイベントを開いていました。顧客管理をきちんとして、さまざまな仕掛け、工夫をしながらファンの囲い込みをしていた。同じように「薬局3.0」では、「無関心客」を「見込み客」にし、さらに「既存客」から「固定客」、「ファン客」というように行動変容してもらう必要があります。
開業医の立場としては当たり前のことで、患者さんはなぜその病院やクリニックを受診するのか。駅前で便利という理由もあるでしょうが、駅前でもつぶれるクリニックはあります。要は医師の技量や人柄、スタッフの対応、院内の雰囲気などで患者さんは選んでいて、薬局もそうあるべきではないかということです。実際そういう方向に進んでおり、特に今回のコロナ禍で、それが可視化されました。いままで当たり前だと思っていた、患者さんが来てくれるということが本当にありがたいことだと薬局の経営者は痛感したはずです。
「薬局3.0」への転換を図るためには、薬剤師の力が非常に重要になりますね。
私は「服用後のフォロー、薬学的アセスメント、医師へのフィードバック」(FAF、ファフ)と言っていますが、薬剤師は患者さんの薬物治療を行う専門家としての立ち位置を確立することが大切になります。対物業務はきちんと行った上で、薬を渡した後、それが効いているかどうかフォローする。渡して終わりではなく、渡してからが勝負です。そのためには「知識・技能・態度」のバージョンアップが大事になります。服用後の患者さんの状態を知るためのバイタルサインに関する技能とともに、そこで得られた患者情報を処方内容と照らし合わせて薬学的に理解し、把握するための知識、そしてそれらの情報を医師にフィードバックし、薬物治療の質を向上させていくための対人スキルが求められます。
FAFを行うことで、薬剤師は薬学的専門性をフルに使うことになります。薬剤師は大学で薬が体に入った後のことを学んだのに、実際の業務では薬が体に入るところまでしか行っていないので、仕事にやりがいが感じられなかったのです。薬を出した後を見るというのは、薬学的専門性が生きます。これはOTC医薬品であっても同じことです。





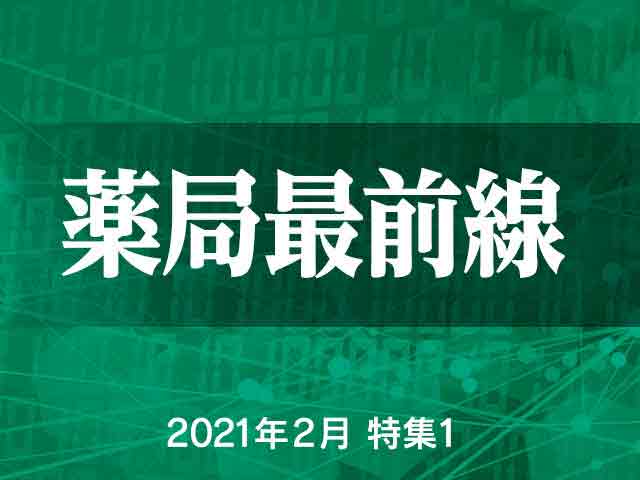





.png?1768543804)
.png?1768543786)




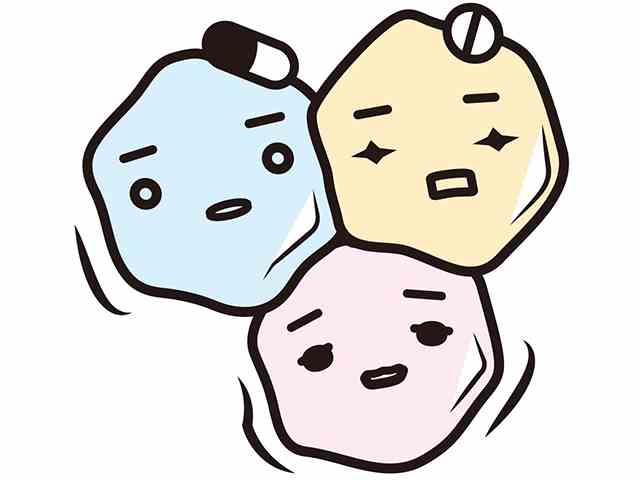


























.jpg?1743033189)