脳梗塞に合併する疾患の管理【2025年改訂版】
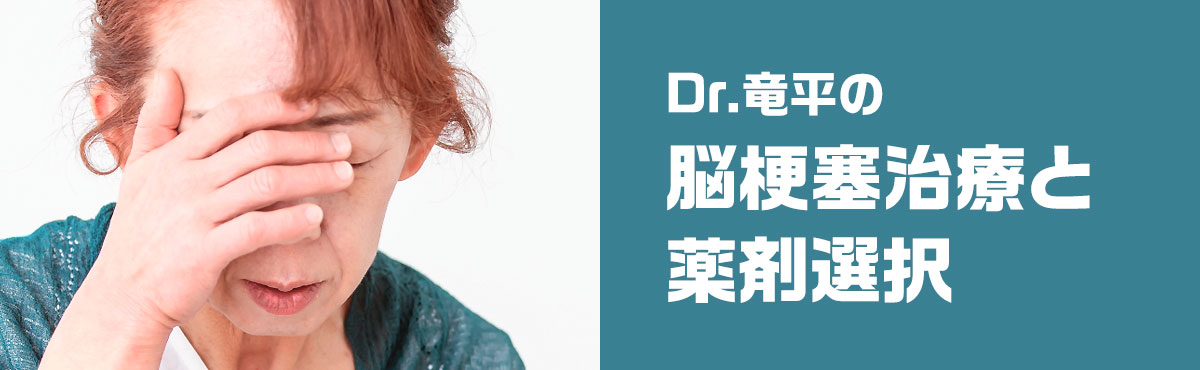
現在、脳血管疾患の総患者数は188万4,000人と言われ、介護要因の疾患トップとも言われています。在宅医療の現場でも、脳梗塞の患者へ服薬指導を行うケースも多いのではないでしょうか。この連載では、内科医の視点から「薬剤師が知っておくと役立つ」脳梗塞の基礎知識や治療の変遷について、できるだけ分かりやすく解説します。今回は脳梗塞患者が合併する疾患(主に生活習慣病)についての管理をお話ししたいと思います。
1. 脳梗塞に合併する疾患とは?
脳梗塞は今までお話しした通り、一度発症してしまえば重篤な後遺症を残す可能性がある疾患です。このため“発症させないこと”が重要であることは言うまでも無いかもしれません。そして脳梗塞を発症してしまっても、2回目の脳梗塞(つまり再発)を起こさないよう対策を取るべきです。
脳梗塞はいろいろな因子が絡み合って発症しますが、やはり生活習慣病をしっかりコントロールすることが大切です。
ちなみに“生活習慣病”という名称は聖路加国際病院の日野原重明先生が提唱したものであり、現状に即したうまい名称だと思います。
具体的には、高血圧、2型糖尿病、脂質異常症が該当します。それぞれの管理方法は内服治療がメインであり、それについて概説していきたいと思います。
2. 脳梗塞に合併する各疾患の管理方法
2-1. 高血圧
高血圧症の患者数は4,300万人と言われており1)、日本人の2〜3人に1人が罹患している非常に患者数の多い疾患です。血圧がやや高いだけでも脳・心血管疾患発症は約3.5倍になるとされています2)。
高血圧症は動脈硬化を促進させるため脳血管障害において管理することは非常に重要です。ここでは発症予防と発症してからの管理を見ていきたいと思います3)。
[発症予防]
・75歳未満、冠動脈疾患、蛋白尿陽性のCKD、糖尿病、抗血栓薬服用中の場合
→130/80mmHg未満で管理
・75歳以上、両側頚動脈狭窄や主幹動脈閉塞がある場合、蛋白尿陰性のCKDの場合
→140/90mmHg未満で管理
内服としてカルシウム拮抗薬、利尿薬、ACE阻害薬、ARBなどが勧められます。どれを選択するかは各人の身体状況や合併症の有無などにより選択されるため、疑問が生じた際には担当医と疎通を取り合うと良いでしょう。




















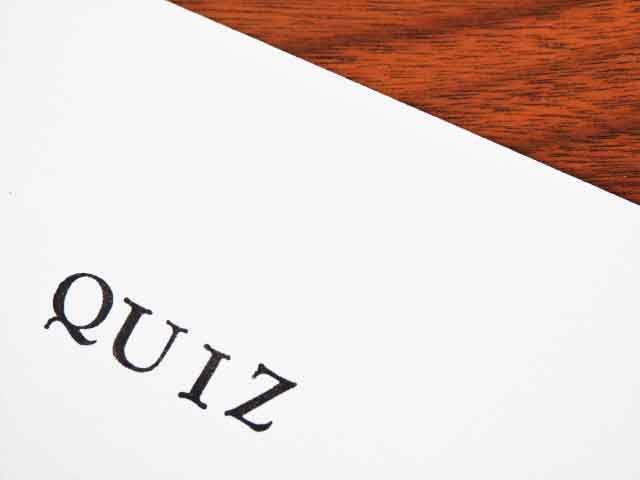




.png?1764143611)























.jpg?1743033189)