地域包括ケアシステムとは?目的や特徴、取組事例までわかりやすく解説

待ったなしの状態で高齢化が進むなかで、高齢者を支えるしくみとして、地域包括ケアシステムの必要性が高まっています。
地域包括ケアシステムの特徴は、政府や地方自治体だけでなく、高齢者自身や地域のコミュニティも積極的に関わって、地域全体で持続可能なよりよいケアのしくみを作っていくところにあります。
ここでは、地域包括ケアシステムのしくみや目的、メリットについて、事例もまじえながらわかりやすく解説します。
地域包括ケアシステムとは

図・厚生労働省「地域包括ケアシステム」より引用
地域包括ケアシステムとは、高齢者が要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、地域内で必要な支援が連携して提供される体制のことです。
急速に高齢化が進むなかで、厚生労働省は、団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に地域包括ケアシステムを実現するとしています。
これまで縦割りだったシステムを改め、医療、介護、生活支援、介護予防、住まいを包括して一体的に支援するのが、地域包括ケアシステムです。
地域包括ケアシステムの目的
地域包括ケアシステムの主な目的は、高齢者が住み慣れた地域で、自立した生活をできるだけ続けていくのを支援することです。
高齢者をきめ細やかに支援していくためには、高齢者が住んでいる地域が主体となる必要があります。高齢者への支援が破綻することなく続けていけるよう、その地域の特性を踏まえて、医療・介護・生活支援資源を効率的に活用していかなければなりません。
この場合の「地域」とは、おおむね30分以内に介護や医療サービスの提供ができる日常生活圏域(中学校区域)とされています。その市区町村の地域包括支援センターやケアマネージャーが主体となります。
地域包括ケアシステムが必要な背景
日本では、世界でも前例のない早さで高齢化が進む一方で、出生率は下がり、労働人口は減少していきます。
高齢者介護への対策は、これまで国が主導権を取って進めてきました。
しかし、超高齢化が進み、団塊の世代が後期高齢者になると、介護の担い手が足りなくなり、これまでのやり方では増加する介護ニーズに対応できなくなってしまいます。
また、「高齢化」「介護」といっても、地域によって高齢化の割合も違えば、使うことのできる介護リソースも異なります。
これまでは、たとえば一人暮らしをしていた高齢者について、介護度が進むと施設に入居せざるをえない、というのが一般的でした。
しかし、必要な支援を受けることができれば、自宅で一人暮らしを続けることも可能だという認識が広まってきました。ただ、そのためには、高齢者一人ひとりに応じたケアを提供しなければなりません。
そのような状況では、国が一律で号令をかけるよりも、それぞれの地方自治体が、自分たちの状況に合わせた施策を立て、実行していく方が有効です。
このような背景のもとに、地域が中心となって介護問題に対応する地方包括ケアシステムが必要とされるようになったのです。
地域包括ケアシステムを構築するメリット
地域包括ケアシステムを構築することにはどのようなメリットがあるのでしょうか。
高齢者が自宅で過ごせる
これまで、自宅で暮らす、地域で生活するということは、心身が健康で、自分で稼ぎ、身の回りのことをするということが前提となっていました。
高齢になると、病気になれば病院、要介護状態になれば介護施設に入ることが当たり前で、要介護の高齢者が自宅で過ごすためには家族の負担に頼っているのが実情でした。
地域包括ケアシステムが機能していると、自宅にいても必要な介護や医療、生活面でのケアを受けられます。
たとえ一人暮らしであっても、介護サービスを利用しながら住み慣れた自宅に住み続けることが可能になります。
高齢者の生活のクオリティが上がる
地域包括ケアシステムでは、介護が必要になってからのケアだけでなく、要介護状態になる前にいかに健康寿命を延ばすか、高齢者の生活のクオリティを上げることも重視されています。
自宅に引きこもりがちな高齢者の社会参加を促し、他の高齢者との交流を増やすことで、高齢者の心身の健康を守ることができるのです。
健康な高齢者が増え、不調を感じたときに早期に対応できれば、介護や医療の負担を軽減することにもつながります。
高齢者の家族の負担が軽くなる
在宅で介護をしようとすると、同居する家族の負担がどうしても重くなります。特に現代は高齢者が高齢者を介護する「老老介護」も問題となっています。
これまでは家族が介護の中心として身体的なケアも精神的な責任もすべて担っていました。しかし、地域包括ケアシステムが機能すると、家族もケアマネジャーなどと相談しながら必要なケアを判断し、介護の見通しを立てることができます。
介護ヘルパーを依頼したり、一時的に介護施設を利用したりすることで、身体的な負担も軽減することができるでしょう。
家族の負担が減ることは、高齢者の幸せにもつながります。高齢者と家族が共に幸せに住み慣れた自宅で過ごすことができるのです。
人材の有効活用が促進される
要介護高齢者の増加に対して、若年層の人口が減少していく中にあって、これまでと同じレベルで医療や介護の専門職を確保することが難しくなっている現状があります。
地域包括ケアシステムでは、老人クラブや自治体などの住民同士の助け合いやボランティアが重視されています。
高齢者を単にサービスを受ける側と定義するのではなく、元気で能力のある高齢者には積極的に社会活動をしてもらい、ケアの担い手側に回ってもらいます。そうすることで、専門家はよりニーズの高い分野に集中することができるようになるのです。
地域包括ケアシステムの5要素
地域包括ケアシステムでは、次の5つの要素が連携して機能することが重視されています。
順番に解説していきましょう。
1.医療
地域包括ケアシステムでの医療の特徴は、日常的な医療と緊急時の医療という2本立てで考えられていることです。
普段の生活での病気については、かかりつけ医を中心とした地域の医療が担います。かかりつけ医に健康状態を把握してもらいながら、調子が悪くなったら地域の連携病院で診てもらう、というように、地域のなかで必要なケアを受けていきます。
そして、大きな病気やけがの場合は、急性期病院で治療を受けることになります。
このように、地域と総合的な病院で役割を分担することで、医療リソースへの負担が軽減され、必要な医療を必要なときにスムーズに受けられるようになるのです。
2.介護
介護についても、在宅系サービスと施設・居住系サービスの2本立てで考えられています。
在宅系のサービスには、訪問介護、訪問看護、通所介護、小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護、24時間対応の訪問サービスなどがあります。
在宅で利用するものと通所するものを組み合わせた複合型サービス(小規模多機能型居宅介護+訪問看護)も利用できます。
施設・居住系サービスには、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症共同生活介護、特定施設入所者生活介護などがあります。
在宅支援を利用しながらできるだけ自宅で生活し、要介護度が進んで自宅での介護が難しくなったら施設を利用する、ということもできます。その場合も、地域内で連携が取れているためスムーズに対応できるでしょう。
3.生活支援
地域包括ケアシステムで重視されているのが生活支援です。
これまでは個人で自立して行うのが当然とされていた日常生活についても、必要なサービスを受けることで、高齢になっても自宅で生活を続けることが可能になります。
生活支援には以下のようなものがあります。
- 食事の準備や掃除、洗濯などの家事支援
- 食事の宅配
- 通院や外出をサポートする移動支援
- 地域のイベントや趣味のサークルなどの地域交流の支援
- 認知症カフェ
- 一人暮らしの高齢者への見守り、安否確認
- 食品などの移動販売
これらの生活支援には、医療や介護と違って専門的な資格は必要ありません。
自治体、老人会、NPO法人、ボランティア、そして民間企業などが担い手となります。
さまざまな団体が連携しながら、高齢者がコミュニティのなかで心身ともに健やかに生活するための支援が行われることが期待されています。
4.介護予防
これまでは介護が必要になってからの支援が中心となっていましたが、介護予防にも重点を置くようになったことも地域包括ケアシステムの大きな特徴です。
日本人の平均寿命は長くなりましたが、健康上の問題で制限を受けることなく生活できる期間である健康寿命との間には約10年の差があります。
この差を短くして、健康で自立して生活できる期間を増やすことが、高齢化社会では重要になります。
介護予防のために、体力保持のための体操教室や、食事や栄養に関する専門家からの指導などが行われています。
また、さまざまなイベントやサークル活動のために外出し、コミュニティのなかで仲間と交流することそのものが介護予防につながります。
5.住まい
地域包括ケアシステムにおける「住まい」には、自宅だけでなくサービス付き高齢者向け住宅などの施設も含まれます。
安心して地域で暮らしていくためには、生活のベースとなる住まいが安定していることが大切です。自宅だけでなく住まい全般に関しても幅広くケアしていこうというのが地域包括ケアシステムの特徴です。
高齢者が住む場所に困らないよう、高齢者住宅や施設の確保、拡充が行われます。
地域によっては、増え続ける空き家を高齢者向け住宅として有効活用しようとする動きもあります。
また、賃貸住宅に入居する際に必要となる保証人を確保するなどといった手続き関係の支援も、地域包括ケアシステムには含まれます。
地域包括ケアシステムの自助・公助・互助・共助という考え方
地域包括ケアシステムで重視されているのは、4つの「助」です。
4つの「助」とは、「自助」「公助」「互助」「共助」を指します。
それぞれの「助」の内容についてみていきましょう。
自助
「自助」とは、自分で自分を助けることです。
自分の健康のために、食事に気を配ったり、日常的に運動を行なったりするセルフケアや、必要なものを購入したりすることも含まれます。
公助
「公助」とは、高齢者対策だけにとどまらない、政府や地方自治体による社会福祉制度のことです。税金をもとに提供されるもので、生活保護などが該当します。国民全体に関する生活困窮者や貧困への対策として行われ、そのなかで生活の苦しい高齢者も対象となります。
互助
「互助」とは、家族や友人、地域住民の間の助け合いです。
現役時代は会社や仕事が中心だった高齢者の場合、会社での関係がなくなると、家族以外の人間関係がないという人も少なくありません。
家族だけでなく、地域のコミュニティの中で友人や仲間を作り、助け合っていくことが大切だといえます。
共助
「共助」とは、介護保険や医療保険サービスなどの制度に基づく相互扶助のことです。
「互助」と同様に社会全体で相互に支え合うしくみですが、政府によって制度として運用されているものが「共助」となります。
これらの「助」が互いに連携し、高齢者が自らの力を活用しながら、公的な支援と地域社会の協力を通じて、お互いに支え合うことが大切です。
各自治体の取り組み例
地域包括ケアシステムでは、それぞれの自治体が、地域の実情に合った支援体制を構築していくことが重要になっています。
一口に「支援」と言っても、都会と地方では高齢化率も、使うことのできる介護リソースも異なります。
また、離島や人口減少が著しい地域はますます厳しい状況にあります。
そのような状況のなかで、各自治体は、それぞれの地域の特性を生かして、必要な支援を準備していこうとしています。
ここでは、厚生労働省の資料から、先進的な市町村の取組事例をご紹介します。
※厚生労働省発表資料「【シンポジウム用溶け込み】地域包括ケアシステム構築モデル事例」の「地域包括ケアシステム構築へ向けた取組事例」より引用
千葉県柏市

千葉県柏市では、在宅医療を推進するために、行政である柏市が事務局となり、医師会や薬剤師会、訪問看護連絡会などと連携した体制を構築しています。
医療と介護の関係者が定期的に会合を持って情報交換することで、在宅介護に連携して当たることができます。
鳥取県南部町

鳥取県南部町では、地域のなかのつながりが薄い一人暮らしの高齢者が増えていることが問題になっていました。
そこで、民家や公共施設を改修して、地域の住民組織が運営する高齢者の共同住宅を設置。
地域住民が見守りや食事の提供などの生活支援サービスを提供し、必要に応じて訪問医療や訪問介護を受けられるようになっています。
年金受給額が低くても安心して住み慣れた地域で暮らせる、「第三の住まい」を提供しています。
大分県竹田市

大分県竹田市では、介護予防に重点を置いた事業が推進されました。
暮らしのサポートセンター、久住「りんどう」を立ち上げ、介護予防サービスと生活支援サービスを提供。
対象となったのは自立から要介護2までの高齢者で、健康づくりのための運動やレクリエーション、調理教室などを実施。生活支援としては、配食サービスや服薬確認などが提供されています。
「りんどう」はボランティアである暮らしのサポーターがスタッフとして関わっていますが、サービス利用者も暮らしのサポーターも同じ「会員」であることが特徴です。
新潟県長岡市

新潟県長岡市では、法人が主導していた介護体制を改め、官民が連携することで介護ニーズに応じた地域包括ケアシステムの構築が行われました。
市内を小さな区域に分け、そのなかで必要な支援が受けられるように再整備されました。
市内中心部に13カ所のサポートセンターを設置し、サポートセンターごとに医療や介護サービスを提供することで、よりきめ細やかな支援が可能となっています。
熊本県上天草市

熊本県上天草市の湯島地区では、高齢化率が高いにも関わらず、離島であるため介護サービス提供者がいない状態でした。そのため、離島という条件に応じた在宅支援サービスの整備が行われました。
高齢者のいる全世帯でどのような支援が必要かを調査し、必要なサービスを把握。緊急通報システムが配置され、配食サービスを行う見守り隊が始動しました。
地域内で介護ヘルパーの養成も行われ、高齢者が地域で暮らし続けるしくみ作りが進んでいます。
高齢化が進む一方で、若年層の人口が減少し、介護の担い手が不足するなかで、介護や医療のプロだけに頼るのではなく、地域のさまざまなリソースを有効に活用してサービスを提供していくことが喫緊の課題となっています。
また、高齢者を単にサービスを受ける受給者と位置づけるのではなく、コミュニティの一員として自助や互助を促すことで、健康寿命を延ばし、生活のクオリティが上がり、高齢者自身の幸せにつながることも期待できます。
これからの地方において、地域包括ケアシステムの役割は大きいといえるでしょう。








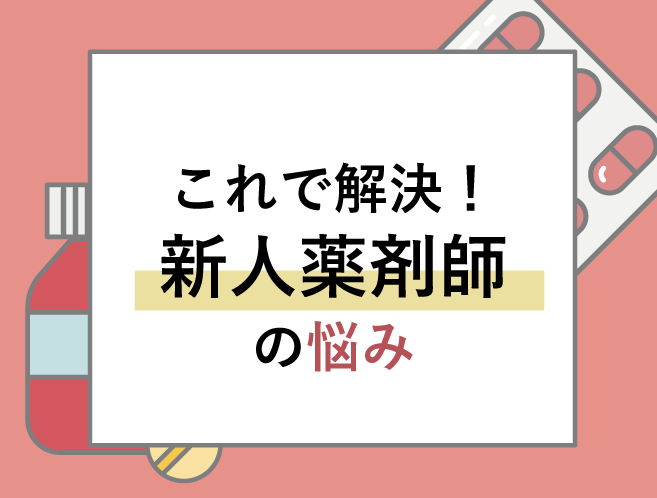














.png?1716358083)

























