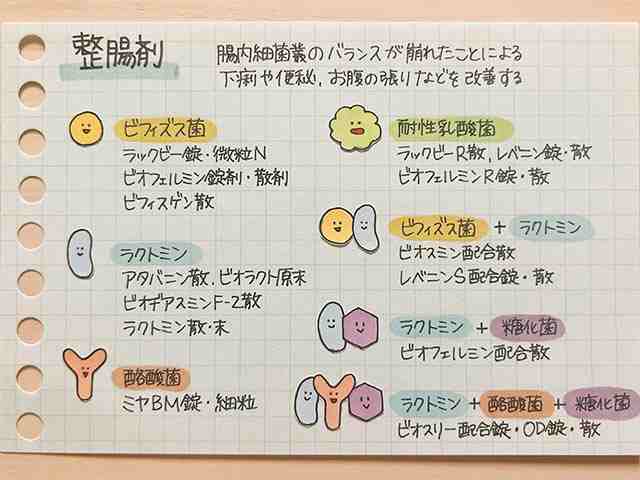【2024年度改定版】退院時共同指導料の算定要件や改定内容をわかりやすく解説

高齢化が進み、在宅医療の需要が近年ますます高まってきています。患者が退院後にスムーズに在宅医療を始められるよう、多職種が積極的に情報共有を行い、連携しながら進めていくことが非常に重要です。
本記事では、退院時共同指導料の算定要件や留意点、算定できないケースについて詳しく解説していきますので、算定を目指す際の参考にしてみてください。
退院時共同指導料とは
退院時共同指導料とは、患者が退院後にスムーズに在宅医療を受けられるよう、関係医療職種が合同でカンファレンス等を行うことによる、円滑な情報共有や支援を評価するものです。
以前の算定要件では、共同する職種として医師や看護師のみが挙げられていましたが、2022年度診療報酬改定において多職種連携の重要性が見直されたことにより、薬剤師を含めた多くの職種が追加されました。
薬局薬剤師も地域医療を支える存在として、入院中の薬物治療の経過を知ることで、その後の在宅訪問薬剤管理指導にいかしていくことが求められています。
退院時共同指導料の算定要件
退院時共同指導料は、退院後の訪問薬剤管理指導を実施する薬局の薬剤師が、入院先の医療機関に赴き、退院後の在宅での療養上必要な薬剤に関する説明および指導を、医療機関の関係医療従事者と共同して行った場合に算定ができるものです。
退院時共同指導料の算定要件
| 算定点数 | 600点 |
| 算定対象患者 | 保険医療機関に入院中の患者※ |
| 算定上限回数 | 当該入院中1回に限り算定 (別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、2回算定可能) |
| 算定タイミング | 指導を実施したタイミング |
| 算定条件 | 1)退院後の訪問薬剤管理指導を担う保険薬局の薬剤師が指導を行う。 2) 原則として患者の入院先に赴き、患者の同意を得る。 3) 入院先の医療機関の以下の医療関係職種と共同して、在宅での 療養に必要な薬剤に関する説明・指導を患者や家族等に対して行う。 ・保険医 ・看護師 ・薬剤師 ・管理栄養士 ・理学療法士 ・作業療法士 ・言語聴覚士 ・社会福祉士 4) 患者に対して、指導内容について文書により情報提供をする。 |
※入院の定義については、医科点数表の第1章第2部通則5 に定める入院期間が通算される入院のことをいう。
参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省
退院時共同指導料以外の薬学管理料について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
算定のタイミングは指導を実施したとき
退院時共同指導料の算定タイミングは、指導を行った時点とされています。
そのため、合同カンファレンスを実施後、患者や家族等に指導を実施した日に算定が可能です。患者本人だけではなく、家族や退院後に患者の看護を担当するものに対して指導を行った場合にも算定することができます。
処方箋受付による算定ではないため、算定する際に処方箋受付回数は計上せず、別のレセプト上で退院時共同指導料のみ算定するようにしましょう。
共同指導にオンラインで参加も可能
退院時共同指導料は、保険薬局の薬剤師がビデオ通話により共同指導をした場合でも算定が可能です。
ただし、患者の個人情報をビデオ通話の画面上で共有する際は、患者の同意を得ていることが必須です。
また、医療機関の電子カルテ等の医療情報システムと共通のネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合には、厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 」に対応していることも求められています。
参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省
薬剤服用歴等へ必要事項を記載
退院時共同指導料を算定する際は、以下のことがらについて適切に記録を残すようにしましょう。
【薬剤服用歴への必要な記載事項】
- 入院保険医療機関において患者に対して行った服薬指導等の要点を記載
- 患者またはその家族等に提供した文書の写しを薬剤服用歴等に添付
参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省
退院時共同指導料を2回算定できる患者
退院時共同指導料は、原則当該入院中1回に限り算定と定められていますが、別に「厚生労働大臣が定める疾病等の患者」については、2回まで算定が可能です。
具体的には以下に該当する患者が対象とされています。
別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者
(1)末期の悪性腫瘍の患者(在宅がん医療総合診療料を算定している患者を除く)
(2)「ドレーンチューブまたは留置カテーテルを使用している状態」、または「人工肛門または人口膀胱を設置している状態の患者」のうち、以下のいずれかを受けている患者
- 在宅自己腹膜灌流指導管理
- 在宅血液透析指導管理
- 在宅酸素療法指導管理
- 在宅中心静脈栄養法指導管理
- 在宅成分栄養経管栄養法指導管理
- 在宅人工呼吸指導管理
- 在宅悪性腫瘍等患者指導管理
- 在宅強心剤持続投与指導管理
- 在宅自己疼痛管理指導管理
- 在宅肺高血圧症患者指導管理
- 在宅気管切開患者指導管理
(3)在宅での療養を行っている患者であって、高度な指導管理を必要とするもの
出典:特掲診療科の施設基準等の一部を改正する件 令和6年3月5日 /厚生労働省
退院時共同指導料を算定できないケース
共同児退院指導料は以下の場合は算定ができないため、注意が必要です。