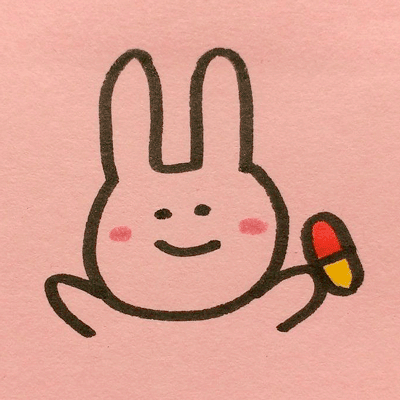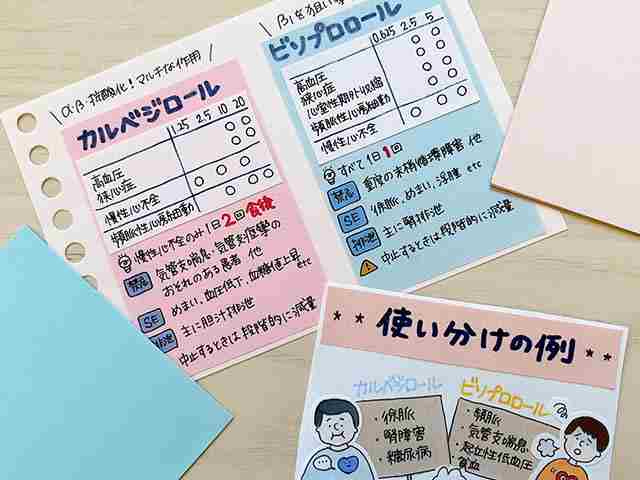【薬剤師向け】褥瘡(床ずれ)ってどんな症状?①基礎編


高齢化に伴って「褥瘡(床ずれ)」のリスクのある患者さんが増えてきています。今回は、日本褥瘡学会のガイドラインをもとに、予防方法や治癒の経過についてまとめました。
褥瘡(床ずれ)ってどんな症状?
褥瘡は、長時間同じ姿勢でいることにより、皮膚やその下の組織に持続的な圧迫が加わり、血流障害が起こることで発生する皮膚トラブルです。特に寝たきりの患者さんや、体の動かしにくい方に多く見られるため、予防と早期対応が非常に大切とされています。

褥瘡(床ずれ)になりやすい人の特徴とは?
日本褥瘡学会のガイドラインでは、褥瘡のリスクとして、体位変換が困難なこと、栄養状態の低下、皮膚の乾燥や過度の湿潤状態などが挙げられています。
また、うっ血性心不全や糖尿病、骨盤骨折、脳血管疾患などの疾患も褥瘡になりやすいため注意が必要です。
褥瘡(床ずれ)の重症度分類はどのように判断する?
褥瘡の重症度分類にはNPUAP/EPUAP分類やDESIGN-R2020が用いられることが多いです。
NPUAP/EPUAP分類では、消失しない発赤が見られるステージⅠ、皮膚の部分欠損が認められるステージⅡ、真皮を超えて皮下組織にまで損傷が及ぶステージⅢ、皮膚全層および骨や筋肉にまで影響を及ぼすステージⅣ、皮膚が紫色や栗色に変化する「深部組織損傷(DTI)疑い」、壊死組織によって深達度が判定できない「判定不能」に分けられています。
褥瘡(床ずれ)のできやすい部位はどこ?
褥瘡は、特に骨が皮膚に近い部位に発生しやすいとされています。
具体的には、仙骨部が最も報告が多く、他にかかと、坐骨部や肩甲骨周辺などが代表的な部位です。その他、肘、頭部、足関節周辺なども、体重が集中しやすく圧迫が起こりやすい場所です。
これらの部位は、長時間同じ姿勢でいると圧力がかかり続け、局所の血流が悪くなるため、早期に対策を講じることが重要になります。
褥瘡(床ずれ)にならないための工夫とは?
褥瘡の発生を未然に防ぐためには、まず体位変換が基本となります。
一般的には、2時間ごとの体位変換が推奨されており、これにより同じ部位への圧迫を避けることが可能です。また、体圧分散マットレスやクッションの使用は、局所にかかる負担を軽減する上で非常に有効です。