薬剤師必読!NSAIDsで「急性腎障害」が起こる時と起こす人とは?

- NSAIDsによる「急性腎障害」のリスクが高くなる患者背景(薬の投与量・期間、年齢、腎機能、併用薬)
解熱鎮痛薬としてよく用いられる「NSAIDs」と「アセトアミノフェン」ですが、一般的に「NSAIDs」は効果、「アセトアミノフェン」は安全性に優れているとされています1)。
今回は、効果に優れる「NSAIDs」ではなく、あえて「アセトアミノフェン」が優先して使われるのはどんな状況か、解熱鎮痛薬の使い分けにおいて薬剤師が押さえておきたいポイントを紹介します。
「アセトアミノフェン」と「NSAIDs」の「急性腎障害」リスク
「NSAIDs」が阻害する「プロスタグランジン」は、腎臓にある糸球体の輸入細動脈の拡張にも関わっています。そのため、NSAIDsを使うと糸球体の輸入細動脈は収縮し、腎臓への血流量が少なくなります。この腎臓の虚血状態が「急性腎障害」の原因となることがあります1)。
実際、NSAIDsの使用と急性腎障害の発症は関連が指摘2)されており、日本でも急性腎障害の原因薬として報告されている薬剤が存在します3)。
一方で、「アセトアミノフェン」ではこうした急性腎障害との関連は確認されておらず4)、胃だけでなく、腎臓にも“やさしい”薬と言えます。このことから、急性腎障害のリスクを避ける目的でもアセトアミノフェンを選ぶことがあります。
しかし、胃粘膜傷害のときと同様、リスクがあるからといって、腎障害のリスクを抱えている人には全てアセトアミノフェンを選んでおけば良い、というわけではありません。
急性腎障害のリスクも薬の使い方や患者背景によって大きく変わるため、患者さんごとにそのリスクの大きさを個別評価する必要があります。
「NSAIDs」の曝露量が多い:「急性腎障害」リスクが高くなる状況①
胃粘膜傷害と同様に「急性腎障害」も、「NSAIDs」の投与量が多い、投与期間が長いほどリスクは高くなる傾向が確認されています5)。
そのため、他にも色々なリスク要因を抱えている患者さんの場合には、漫然と使い続けることを避ける、必要最低限の期間に絞って用いるといった使い方を考える必要があります。



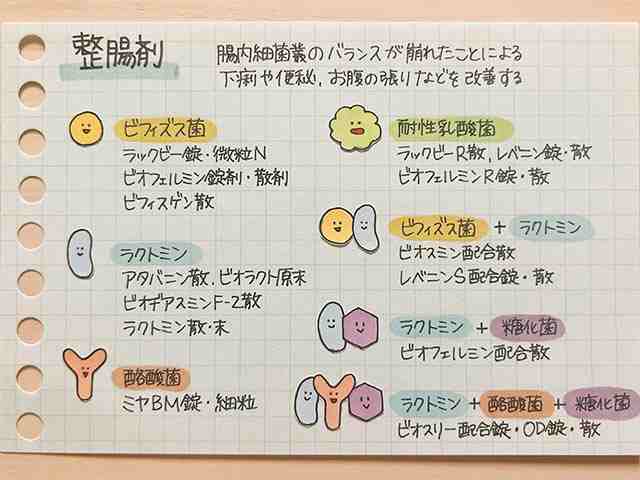




















.png?1764143611)













.png?1765758785)
.png?1765760030)


