薬剤師が飽和状態というのは本当か、現状と今後の見通しを解説
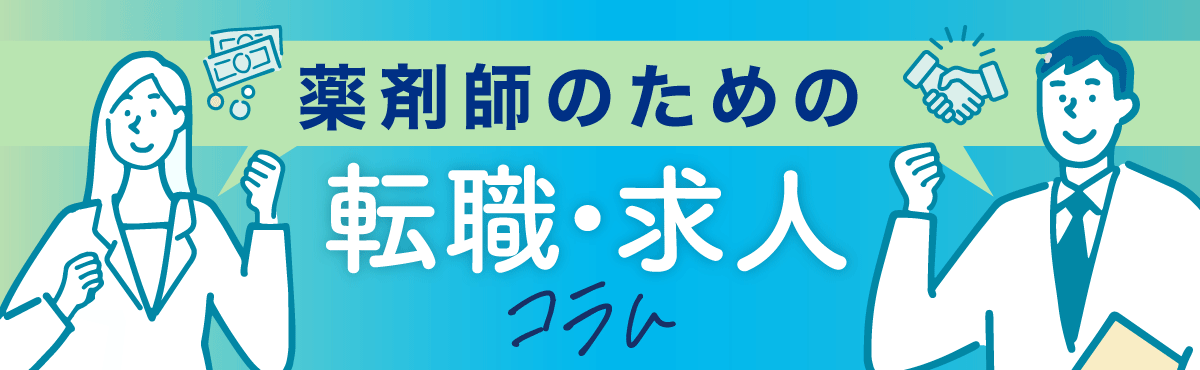

薬学部が増え、薬剤師の数が増え続けているために、薬剤師が飽和状態になると耳にしたことはないでしょうか。業務のデジタル化やAIの進展もそれに拍車をかけるようなイメージがあります。
せっかく職に困らないと思って薬剤師になったのにと不安に感じることもあるかもしれません。
薬剤師は本当に飽和状態になってしまうのでしょうか。
本記事では、薬剤師の需要と供給について、現状の課題や今後の変化を整理しながら、本当に飽和してしまうのかを確認します。また、併せて選ばれる薬剤師となるために必要なスキルや働き方について考えていきます。
薬剤師の転職はこちら
(エムスリーキャリア)

【現在】いま薬剤師は飽和状態にある?

まず、現在薬剤師は飽和状態にあるのかをデータから確認してみましょう。
有効求人倍率から飽和状態かどうかをみる
薬剤師の労働市場を評価する一つの指標として「有効求人倍率」があります。
有効求人倍率とは、ハローワークにおける「有効求人数」を「有効求職者数」で割って求める値です。この数値が高いほど、1人の求職者に対する求人が多いことになり、労働者に有利な市場とされています。
では、現在の有効求人倍率を確認してみましょう。
2024年9月の医師や薬剤師 の有効求人倍率は2.20倍となっています。
現在、社会全体で人手不足が問題だと言われていますが、全体の有効求人倍率は1.11 です。それに比べると、薬剤師の求人倍率は高いと言えるでしょう。
薬剤師の有効求人倍率の変化
厚生労働省のデータをもとに、薬剤師の有効求人倍率の変化をみていきましょう。
医師・薬剤師等の有効求人倍率
| 年月 | 有効求人倍率 |
| 2016年9月 | 5.92 |
| 2017年9月 | 5.25 |
| 2018年9月 | 4.40 |
| 2019年9月 | 3.49 |
| 2020年9月 | 2.01 |
| 2021年9月 | 1.91 |
| 2022年9月 | 2.00 |
| 2023年9月 | 2.15 |
| 2024年9月 | 2.20 |
引用元:一般職業紹介状況 /職業安定業務統計
この表からわかるように、2016年9月の有効求人倍率は5.92倍という非常に高い数字でした。
その後の推移を見ると、2018年9月は4.4倍、2019年9月は3.49倍とゆるやかに低下していきます。
その流れを決定づけたのが2020年のコロナ禍でした。全国的に受診控えが起こり、薬剤師の雇用にも大きな影響がありました。2020年9月の有効求人倍率は2.01へと急激に減少しています。
その後、社会はコロナ禍から回復していきますが、薬剤師の有効求人倍率はコロナ禍前の数値には届いていません。2024年までは約2倍の水準で推移しています。
このように、薬剤師の有効求人倍率は昔に比べると低下しています。「薬剤師は売り手市場で職に困らない」というのはコロナ禍前のイメージと言えるかもしれません。
しかし、先ほど確認したように、求人倍率は全体平均よりも高い状態で安定しています。医療職の国家資格である薬剤師の需要そのものは一定の水準が保たれると考えられるでしょう。
薬剤師が飽和しているかは地域によって違う
薬剤師が飽和しているかどうかは、都市部と地方で違いがあります。
薬剤師の偏在は国としても課題となっており、2023年に厚生労働省は「薬剤師偏在指標」をまとめています。薬剤師偏在指標とは、医療ニーズに基づいて地域ごとの薬剤師数の多寡を判断できるように計算された指標です。
次の表は、薬剤師偏在指標を地域別にランキングにしたものです。数値が大きいほうが薬剤師の数が多く、飽和状態にあると言えます。
地域別薬剤師偏在指標

引用元:薬剤師偏在指標の算定について/令和5年3月29日 第13回薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会 /
厚生労働省
ランキングの上位には東京、神奈川、兵庫のような都市部、下位には地方が並んでいます。
薬学部のある大学は都市部に多く、新卒の薬剤師はそのまま都会で就職する傾向があります。それも薬剤師の偏在の原因です。
このように、薬剤師は都市部は飽和状態医にある一方で、地方は依然として人手不足の状況にあることがわかります。
【将来】薬剤師は今後飽和状態になる?

将来的に薬剤師が飽和状態になるかもしれないということを、国も問題視しています。
ここからは、厚生労働省の2021年に発表された「薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会 とりまとめ(提言概要) 」を中心に、今後の薬剤師の労働市場についてみていきましょう。
次のグラフは、薬剤師の将来の需給状況を予想したものです。

引用元:薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会 とりまとめ(提言概要) /厚生労働省
この表によると、将来的には薬剤師の供給が需要を上回るとされています。現在の状況が続くと、薬剤師は飽和状態になると予想されているということです。
薬剤師が飽和状態になる理由

このように薬剤師が飽和状態になるのはなぜでしょうか。その理由を探っていきましょう。
薬剤師の需要が頭打ちになる
これまでは高齢化の進展にしたがって医療のニーズも増大してきました。しかし、今後は少子高齢化が進むことにより、日本の人口は減少していきます。
それに伴って医療全体の需要構造も変化していくと考えられます。薬剤師の需要も一定の水準で頭打ちになる可能性があります。
需要が変わらないのに新卒の薬剤師数が増える
少子化が進む一方で、近年、薬学部は増え、新卒薬剤師の数が増えています。
薬剤師の需要が減少していくなかで薬剤師数が増えれば、供給過多を招き、飽和状態を加速させる原因となります。
登録販売者などの増加
OTC販売がメインとなる職種では、コストが安く採用が容易な登録販売者の採用が増加しています。それに伴い、一般用医薬品の販売業務で薬剤師の役割が縮小するケースが増えています。特に長時間営業のドラッグストア業界では、登録販売者が多くの業務を担うようになりつつあります。
IT化やAIの導入
薬剤師の現場ではIT化やAIの導入が進んでいます。
調剤業務では、分包機や調合ロボットが導入され、正確で迅速な薬剤準備が可能になっています。また、在庫管理もIT化によって効率化されています。
このようなIT化は薬剤師の負担を軽減し、より患者さんとの対人業務に集中することを助けています。ただ、これまで薬剤師が担っていた業務が自動化されることで、人員削減が進む可能性はあります。
薬剤師が偏在している
先ほど確認したように、都市部に薬剤師が集中し、地方では薬剤師が不足しているという偏在の問題があります。この状態が続くと、地方では人材不足でありながら都市部では薬剤師が飽和してしまう恐れがあります。
【職種別】薬剤師が飽和する可能性

薬剤師が飽和するかどうかは、働く場所によっても違いがあります。ここからは、薬剤師の主要な職種ごとに今後の見通しを確認していきましょう。
調剤薬局
調剤薬局は薬剤師が最も多く働いている職種で、これまでは安定したニーズがありました。
しかし、先述した調剤作業の機械化により、調剤薬局での薬剤師の作業は代替されています。また、2019年に厚生労働省から薬局事務員のピッキング作業を認める通達がありました。このような、薬剤師以外でも対応可能な業務はほかのスタッフが担当するという流れは今後も続いていくと考えられます。
そのほかにも、調剤報酬の改定や人口減少に伴う患者数の減少により調剤薬局の経営状況が厳しくなれば、薬剤師の雇用にも影響するでしょう。
このような状況を見ると、調剤薬局における薬剤師のニーズが増えるとは考えにくく、少しずつ減少していく可能性もあります。
ただ、人の健康や命にかかわる重要な業務なので、すべてが機械化されることはないでしょう。また、対物業務から対人業務へという流れのなかで、薬剤師にとっては患者さんとのコミュニケーションの比重がますます増えています。
時代の流れをふまえながら、患者さんに必要とされる薬剤師であることが大切であると言えます。
病院
医療現場で専門性の高い業務を担当する病院薬剤師の未来は比較的安定していると考えられます。
医療現場は日進月歩で、医師や看護師とチームを組んで柔軟に対応できる病院薬剤師の仕事はAIで代替できるものではありません。病棟業務で患者さんに服薬指導を行ったりする対人業務も病院薬剤師の重要な仕事です。
このように、代替不可能な高度な専門知識を持つ病院薬剤師への需要が減ることはないでしょう。
ドラッグストア
医薬品だけでなく小売業の側面も大きいドラッグストア業界は、依然として成長を続けています。薬剤師しか業務を担当できない調剤併設型の店舗も増えており、薬剤師の需要は高くなっています。
それに対して、ドラッグストアは調剤薬局などに比べると薬剤師の就職先として人気がないこともあり、ドラッグストア側の採用意欲は高めです。
ドラッグストアでは、登録販売者や一般のスタッフと一緒に働くことになります。また、日用品の販売や品出しなどの、薬剤師以外の業務もしなければなりません。
このように、ほかの医療現場とは違う特色がありますが、それを前向きに考えることができれば、ドラッグストア薬剤師の未来は比較的明るいと言えます。
一般企業
製薬会社は、グローバル化による海外の企業との競争や、ジェネリック医薬品のシェア拡大によって厳しい状況になると考えられます。業績の影響を受けやすいMRの需要は厳しくなるかもしれません。
製薬会社以外でも、薬を扱う会社や流通の現場では管理薬剤師のニーズがありますが、これらは現在でもそれほど求人は多くなく、今後も大幅に増えることはないでしょう。
薬剤師が飽和しても選ばれる薬剤師になるには

このように、働く場所によって違いがありますが、薬剤師の雇用が昔のように売り手市場に戻ることは難しいでしょう。そのような状況のなかでは、自分なりのアピールポイントを作って、選ばれる薬剤師になることが必要です。
ここでは、薬剤師の側にどのような取り組みが求められるのかをみていきましょう。
薬剤師としてのスキルを深める
たくさんいる薬剤師のなかで選ばれる存在になるためには、薬剤師として基本的なスキルがきちんとしていることが最低条件となります。
まず、薬剤師として基本となる調剤スキルをしっかり身につけておきましょう。そのうえで、在宅医療のプロフェッショナルになったり、資格を取得したりすることが有効です。
コミュニケーションスキルを高める
業務のデジタル化やAIの導入が続く状況では、逆に人間にしかできない患者や医療スタッフとの円滑なコミュニケーションの重要度が高くなります。
単に薬の説明をするだけでなく、患者さんの生活に寄り添い、療養をサポートする薬剤師が必要とされています。患者さんの立場に立って医師とやりとりするスキルも大切です。
地域医療に貢献できる薬剤師になる
高齢化が進むなかで、地域医療における薬剤師の役割が大きくなっています。在宅医療に対応できる薬剤師のニーズはますます高まるでしょう。
地域の医師や介護関係者と連携をとりながら、患者さんに寄り添って在宅医療をサポートすることが薬剤師にも求められています。
かかりつけ薬剤師の資格を取るなどして、地域医療に貢献できる薬剤師となれば、今後も安心でしょう。
新しい技術を使いこなしていく
近年導入が進んでいる調剤マシンや処方箋の電子化などに対応することが難しい、これまでのやり方を続けていきたいと感じている人もいるのではないでしょうか。
しかし、このような流れについていけず、機械やITを使えないとなると、働く場所を狭めることになっていまいかねません。
また、今後はオンライン診療も進んでいくでしょう。
新しい技術に気後れせず、積極的に身につけていくことで、変化する医療業界に適応していきましょう。
地方で働くことも考える
先ほど説明したように、都市部では薬剤師は飽和状態になる一方で、地方では過疎化もあり人手不足が続くことが予想されます。
薬剤師として働き続けるためには、地方でのキャリアを検討するのも一つの選択肢です。地方では薬剤師の需要が高く、安定した職場環境が期待できます。
薬剤師の転職はこちら
(エムスリーキャリア)

まとめ

昔は薬剤師になれば一生安心と思われていましたが、現在の薬剤師の労働市場は徐々に厳しくなっています。すぐに職がなくなることはありませんが、将来においては飽和状態になるかもしれません。
そのような状況のなかで薬剤師として働き続けるためには、時代の流れに逆らわず、必要とされるスキルを身につけることが大切です。また、需要の高い職種や地域を選んでいくことも有効です。
薬剤師が飽和に向かう時代においては、「選ばれる薬剤師」になるための努力が大切になるでしょう。
ご相談は無料です。転職コンサルタントに相談してみませんか?






























